スイスのアートシーン 2022年はどうなる?

2年目となる新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)は、芸術文化に今なお影響を及ぼしている。アーティストや美術館、パフォーマーらが不確実性と継続的な感染対策の中でもがく一方、アート市場は活況だ。その理由は3つのアルファベットに集約される。NFTだ。
NFT(非代替性トークン)、ブロックチェーン、暗号通貨、クリプトマイニング。2021年が終わろうとしている今、金融界はこの話題で持ちきりだ。パンデミック後の世界がどうなるのか、金融界が歓迎するこの次なる革命がどのような影響を及ぼすのか。経済学者たちはその筋書き作りに精を出す。
議論はアート業界でも起こっている。アーティスト、ギャラリスト、アートディーラー、キュレーターたちもこの新しいテクノロジーを理解し、自分たちの市場にどのような影響を与えるのか、考えを巡らせている。
抽象的すぎだと思われるかもしれないが、心配はいらない。デジタル市場におけるデジタルアートは、見かけほど複雑ではない。来年までにはこれが主たる話題になるだろう。
特筆すべきは、NFTの取引がここ数カ月で10億ドルの大台に乗ったということ。数千万ドルで落札された作品もある。そのほとんどが単純な投機、一種のギャンブルで、作品の価値は暗号通貨市場の不規則な変動に大きく連動しているというのがまぎれもない事実だ。一晩で大きな利益を得ようとする投資家が増えているため、来年にはこのバブルが崩壊する可能性もある。
だからといって、NFTが単なる誇大広告だという意味ではない。この現象はアート界に新たな環境を作り出した。より包括的で、アーティストに作品に対するより大きな権限を与え、そして彼らの銀行口座により多くのロイヤリティが入る――そんな可能性を持つ環境だ。
私たちが知るアート市場は過去半世紀に渡り、アートフェアからギャラリー、オークションハウスへと、いうなればエリートたちのサーカスに姿を変えた。アーティストたちはせいぜい「脇役」に追いやられ、作品の価値に全く関与できないシステムに対処しなければならなくなった。このような状況は「システム」の外で活動する新進気鋭のアーティストにとっては、もっと厳しい。
しかし、NFTはこの点で画期的な存在だ。アーティストは仲介者を入れることなく、Opensea外部リンクなどのプラットフォームで作品を直接取引できる。さらに重要なのはブロックチェーン技術によって、作品価格が流通市場で高騰した場合に、アーティストがより多くの報酬を得られることだ。これまでは、アーティストが自分の作品を販売し運よく売れたとして、作品の価値がどれだけ上がろうが、その後の売上の10%しか手にできなかった。NFTは、こうした「古い」世界を大きく変える。

スイスのアーティスト、ピピロティ・リストもつい最近、NFT技術専門のアシスタントを募集する広告を出した。リストのような実績あるアーティストでさえ、自分の作品の販売方法をどう変えるかを考えるようになったのだ。
こうした新しいトレンドに、ギャラリーの対応は分かれる。チューリヒのペーター・キルヒマンのようにNFTに依然消極的なギャラリーもあれば、ペース(米ニューヨーク)やナーゲル・ドラクラー(独ベルリン)のようにデジタル世界で自らの役割を再定義しようとするギャラリーもある。
NFTのプラットフォームは、「オールド・メディア」による公論の独占状態をソーシャルメディアが打ち破ったのと同様、アーティストに新たな選択肢をもたらした。新しいデジタルコレクターは仮想通貨ビジネスの裏表を熟知した若いデジタルネイティブたちだ。しかも暗号通貨の投資領域はまだ限られているため、NFTはクリプト・ミリオネアたちにとって必然の選択肢となる。
もちろん、NFTアートは壁に掛けることはできない(スクリーン上なら可能かもしれない)。しかし、新しい芸術のパラダイムであるNFTは保管・保険の費用がかからない。こうしたコストは大体、機関や個人コレクターの展示予算や維持費を膨らませる一因になっている。
見る人は要注意
スイスは、この波に乗るのが遅すぎたわけではない。むしろ逆だ。スイスはビットコインといったデジタル通貨のより良い規制作りに真剣に取り組んでいる。将来的にはNFTも視野に入れていることは間違いない。
9月にはスイスの証券取引所を運営するSIXグループが、SIXデジタル取引所(SDX)の営業許可を得た。デジタル資産取引のグローバルネットワークを構築する足掛かりとなりそうだ。
ブロックチェーン上の署名によって保証が与えられるとされるものの、この素晴らしい新世界は、完全に安全というわけではない。SWI swissinfo.chのフィンテック専門マシュー・アレン記者は「下手すればNFTは悪夢、うまくやれば良い結果を生む可能性がある。この新しい技術は実験的でペースが速く、そして今は誇大広告に先導されている。有害な組み合わせだ」と指摘する。
主要なプラットフォームの脆弱性、そしていわゆる「ラグプル」(分散型金融で起こる詐欺の一種)は、投資家が特に注意しなければならない。これらはクリプトデベロッパーがプロジェクトを放棄し、投資家の資金を持ち逃げする悪質な手口だ。一方、当局はNFTブームがマネーロンダリング(資金洗浄)や脱税の新たな温床を生むかもしれないと懸念する。
2021年はNFTの影響がアート市場全体で感じられた年だった。夏のアート・バーゼルや秋のアート・バーゼル・マイアミなど主要なアートフェアの来場者がそれを証明した。しかし、アート制作そのものにどのような影響を与えるかは、まだはっきりしていない。この疑問はまだ未解決で、アーティストがこのトレンドにどう対応するかは、2022年中に注視していきたい。
略奪品の返還

2021年は略奪美術品の返還を巡る長年の議論に大きな変化があった。植民地主義時代に宗主国などから略奪され、現在は欧米の主要な博物館や美術館に保管された美術品、美術工芸品のことだ。
今年、英国、ドイツ、フランスの美術館は、既に元の国に権利を委譲した作品の第一陣を祖国に返還した。
アネッテ・バグワティ(チューリヒ、リートベルク美術館外部リンク)やマーク・オリヴィエ・ウォーラー(ジュネーブ美術・歴史博物館)のような著名美術館の館長は既に大きく方向転換し、略奪された美術品を祖国に返すことに前向きだ。だが、スイスはこの植民地関連の騒動から一定の距離を置く。
国内の主要な美術館は今、ナチスの略奪美術品というさらに古い問題と向き合っている。それを代表するのが、チューリヒ美術館新館で今年展示が始まったビュールレ・コレクションだ。作品の出所を再確認するため、歴史家や専門家による独立委員会設置の動きが進むが、当のビュールレ財団はいまだ協力を拒んでいる。

この問題に関する直近の記者会見について歴史家エリッヒ・ケラー氏がこう指摘している。注目すべきメッセージは美術館からではなく、財団の会長で弁護士のアレクサンダー・ヨレスが発したものだった、と。ヨレス氏によれば「略奪美術品、逃避資産、ナチスの迫害による資産の喪失。これらは歴史家の造語に過ぎない。法的な事実とは何の関係もない」。ユダヤ人社会は、このような修辞的な言葉遊びに激昂するようなことはしなかった。スイス系ユダヤ人のアーティスト、ミリアム・カーンは、チューリヒ美術館から自分の作品を引き揚げることを決めた。
一方、同じくナチスに略奪されたとみられる作品群グルリット・コレクションの大部分を保管し、数年前から出自調査に取り組んできたベルン美術館は数週間前、全く異なる姿勢を示した。オットー・ディックスの絵画2点を、略奪か強奪かについての評決が出る前に元の所有者家族に返還することにしたのだ。
秋には、コーネリウス・グルリットの遺産を包括的に紹介する作品展が、同美術館で初めて開かれる予定。同美術館は「作品を調べ、最終的な受け入れは展覧会を伴って行う。ナチス時代の美術商の遺産への対応、それに伴う倫理的な問題への対応という、美術館にとっての試練に取り組む」と、自身の方針を改めて強調した。

ウイルスが許すなら
swissinfo.chは2022年、パンデミック時代の舞台芸術や映画の未来などを注意深く見守っていく。略奪美術品はほかの多くのトピックと同様、2022年も沈静化することはないだろう。最後に、パンデミックが落ち着けばの話だが、2022年は国際美術展の中でも極めて重要なヴェネツィア・ビエンナーレ(4月23日~11月27日)とドクメンタ(6月18日~9月25日、独カッセル)が開催される。
ヴェネチア・ビエンナーレでスイスは非常に高い評価を得ている。今年のスイス・パビリオン外部リンクは、ヴァレー州在住のフランス系モロッコ人アーティスト、ラティファ・エシャックの手に委ねられた。
ドクメンタ15外部リンクでは、インドネシア人アーティストのグループruangrupa外部リンクがキュレーターに任命されたことが大きな見どころだ。ドクメンタの芸術監督は過去、欧州の白人男性ばかりで女性は3人だけ。その旧来モデルと勇敢にも別れを告げたのだ。女性芸術監督はカトリーヌ・ダヴィッド(フランス、1997年)、ルース・ノアック(ドイツ、ロジャー・ビューゲルとの共同キュレーター、2007年)、キャロリン・クリストフ・バカルギエフ(イタリアー米国、2012年)がそれぞれ務めた。スイスの参加はまだ発表されていない。だがこの新たな試みは、スイスや欧州の機関が新しいインスピレーションや手法を模索する中で、確実に刺激となることだろう。それがいずれ、芸術界に残る植民地主義、帝国主義、欧州中心主義の汚点を一掃することにつながるのかもしれない。
(英語からの翻訳・宇田薫)

JTI基準に準拠


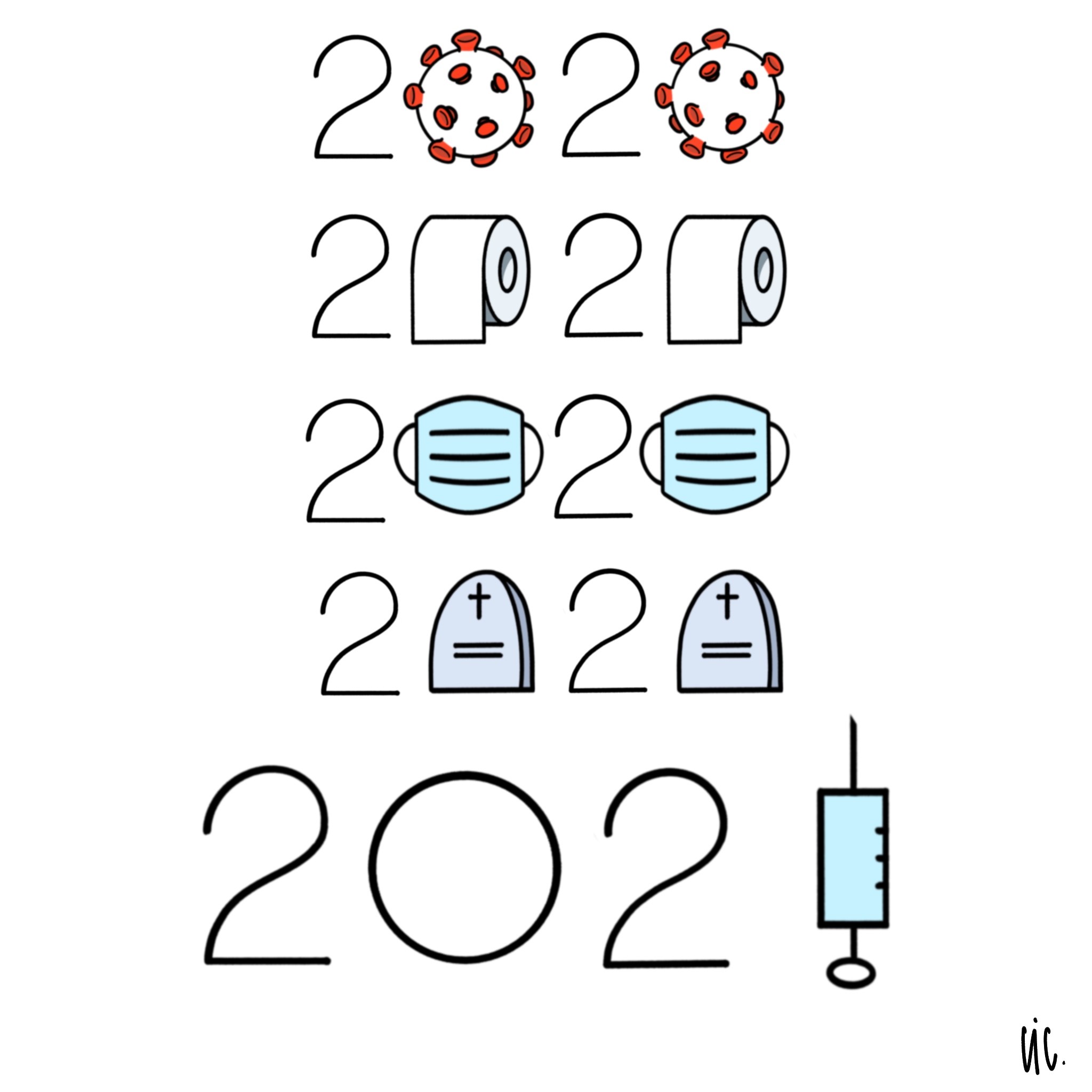
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。