西側が撤退する人道支援システム どこにもいない救世主

これまで人道支援を担ってきた西側の主要ドナー国が後退し、世界の人道支援システムは大きな圧力にさらされている。中国や湾岸諸国などの新興ドナー国が台頭する可能性はあるが、旧来のような国連を介した形ではなくなるかもしれない。
米国は第2次ドナルド・トランプ政権誕生後、人道支援費の大幅カットに踏み切り、それが人道分野の脆弱性を露呈させた。

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
世界の約1億9000万人が拠り所にする国際援助の大部分は米国、ドイツ、欧州連合(EU)、英国が担っているのが現状だ。この4カ国・組織で世界の人道援助の約65%を賄う。
トランプ政権が米国際開発庁(USAID)の携わる援助プログラムの83%を打ち切ったのを皮切りに、多くのドナー国が雪崩を打って対外援助の削減を決めた。
英国は2月末、対外援助予算を国民総所得(GNI)の0.5%から0.3%に削減すると発表。ドイツの新連立政権は3月の連立交渉において、国内総生産(GDP)比0.7%目標を放棄する計画を表明した。
フランス、ベルギー、スウェーデン、スイスなども国際協力・人道支援費の削減を発表した。新型コロナのパンデミックやウクライナ戦争による国防費の増大が国家予算を圧迫したことが背景にある。
一部の国は例外的に対外支援を増強している。ノルウェーは米国の予算カットの煽りを受けたウクライナやNGOへの支援を拡大しているが、何十億ドルに上る不足資金を補うには到底足りない。
米国の代わりとなるのは誰か?
swissinfo.chが取材した専門家たちの多くは、米国の穴を埋める可能性があるのはBRICS諸国(中国、ブラジル、ロシア、インドなど)を率いる中国か、あるいはアラブ首長国連邦、サウジアラビアといった湾岸諸国だと考えている。

ジュネーブ拠点の専門メディア「ニュー・ヒューマニタリアン」の最高経営責任者(CEO)、タマン・アルーダット氏は「BRICS諸国は国際的な認知を求めている。影響力と独立性の強化を狙っている」と語る。
人道援助を「ソフトパワー」として使い、自国のイメージ向上や影響力の強化、国連での被援助国の支持獲得につなげるーーそういった思惑もあるという。
米国がUSAIDのかかわる数千件のプロジェクトを打ち切った後、一部国際メディアは、中国がカンボジア、ルワンダ、ネパールなどで類似プロジェクトの支援を持ちかけたと報じた。
しかし中国は不動産バブルの崩壊で経済が停滞し、米国の完全な代わりにはなれないかもしれない。中国政府が国連主導の支援体制に深く貢献する意思があるかも不明だ。

西側に偏った体制
アルーダット氏は「多国間体制は西側に偏っている。なぜ(非西側諸国である)BRICS諸国が、この体制の中でもっと投資を増やす必要があるのか理解できない」と話す。
この偏りの背景には歴史的な要因もある。第二次大戦後の国連創設時にはグローバル・サウスの多くが植民地であり、体制設計に関与できなかった。
また、いくつかの国連組織のトップは欧米人であり、これが偏見の認識を強めている。たとえば、人道問題調整事務所(OCHA)は伝統的に英国人、世界食糧計画(WFP)は米国人がトップを務めている。
サウジアラビアやアラブ首長国連邦などの湾岸諸国は近年、国連の人道支援機関への主要ドナー国に名を連ね始めているが、多くはアラブ連盟やイスラム協力機構の加盟国(イエメンなど)向けの支援が中心だ。
二国間援助への傾斜
マンチェスター大学のバートランド・テイス教授は「国連の援助システムはコストが高く柔軟性に欠ける。主要ドナーにとっては可視性も低い」と指摘する。
支援先での影響力を強めるためには、二国間援助を増やす方が効果的といえる。その典型例は中国で、2024年の国連人道援助への拠出は約800万ドルと、米国の約100億ドルにはるか及ばない。だが「一帯一路」構想を通じアフリカなどで主に融資型のインフラ整備支援を進めており、2024年の契約総額は1220億ドルに上る(復旦大学調査外部リンク)。
このような援助は経済関係強化と地政学的影響力の拡大が狙いであり、人権尊重などの条件は伴わないのが特徴だ。
人道支援の価値観の再交渉
ジュネーブの人道研究センターのヴァレリー・ゴラン氏は、新興国の関与の増加により人道支援の基本的価値観を討議し直すことになると指摘する。
人道支援に貫かれてきた「公平性の原則」は、国籍、宗教、性別に関係なく、最も必要としている人々に援助を提供するべきだというものだ。だが中国をはじめとする新興勢力は自国の地域に援助を集中投下し「公平性の原則」に相反することがある。
ゴラン氏は、BRICS諸国や湾岸諸国が西側諸国のプログラムを単純に受け継ぐことはないと考えている。人権尊重、環境保護、気候保護、民主主義など、援助供与に付随する条件についても然りだ。
「このような欧米からの援助は、時として議論の余地がある」とゴラン氏は話す。援助プログラムが現地の伝統に反する規範や慣習を押し付ける場合があるからだ。
グローバル・サウスの影響力の増大はその意味では歓迎すべきだが、少数派や生態系保護の観点からはリスクもはらむという。
民間セクターに期待はできるか?
人道関係者の間では、民間セクターへの期待が高まりつつある。企業や財団の資金力は、国家を凌ぐことさえある。
例えばビル&メリンダ・ゲイツ財団は、近年では世界保健機関(WHO)の第2の出資者となっており、欧州諸国を大きく上回る。だが、その影響力の大きさは批判の的にもなっている。
開発支援データを提供する機関「開発イニシアチブ(Development Initiatives)」によれば、世界の人道支援における民間資金(財団、企業、個人)の割合は、2016年の13%から2022年には18%に増加した。
だが今後も民間セクターの支援が増え続ければ、人道支援の倫理原則が後退する危険を伴う。どの企業からの支援が「受け入れ可能」かは、寄付を行う企業の活動内容に左右されることになるためだ。
民間セクターは戦争下にある地域や利益の見込めないところへの投資には関心がない。「ソマリアやスーダン、コンゴ民主共和国の人々を誰が助けるというのか?これらの国では民間セクターが利益を上げられない」(アルーダット氏)
おすすめの記事
編集:Virginie Mangin/sj、独語からの翻訳:宇田薫、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠




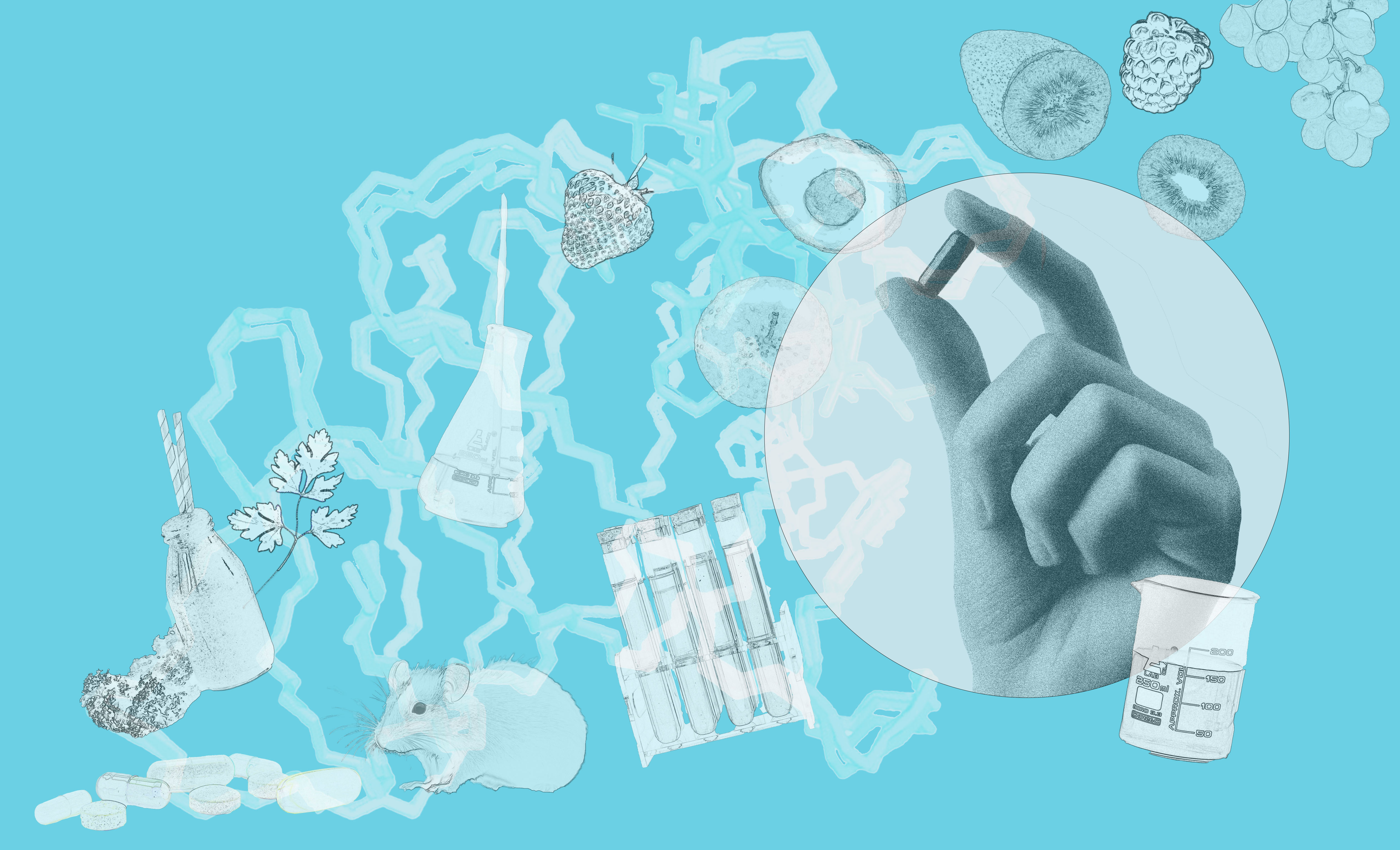








swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。