小さな州が国を動かす? スイス連邦制のしくみと歴史

スイスは26の州と4言語圏で構成される。この多様性を結びつけるのが、1848年に導入された連邦制だ。
スイスの連邦制は、スイス政治システムの支柱だ。
スイスは4言語圏から成り、意思により形成された国家であると自認する。日本など統一の文化・民族によって定義される国々とは対照的だ。
この国家観の起源は、中世に州と地域の間に結ばれた同盟関係にさかのぼる。英語の「federal」の語源であるラテン語の「foedus」は、「同盟、結束」を意味する。
4週間の内戦(分離同盟戦争)を経て、1848年に近代スイスは連邦国家として産声を上げた。「国家連合」から「連邦国家」に移行したが、これは内戦に敗れた保守派の小規模州から不平を買った。
連邦制を採ったのは、国家の樹立を望んでいなかった保守派への譲歩だった。保守派の意見・利益を政治に反映させるためだ。
スイス国民に根付いた連邦制
連邦制は今日までスイス国民に高く評価されている。豪グリフィス大学は2021年に発表した研究外部リンクで、憲法に盛り込まれた連邦制の特徴に対する国民の評価を、連邦制・非連邦制の8カ国で比べた。「分権」「地域ごとの法体系」「地方の国政参加」「連邦・州政府が互いを尊重」の4点について、スイスは総合で最も評価が高く、ベルギーでは最も低かった。
特に、スイスは「地方も国政に参画する」ことに対する理解が最も広く浸透している。
「異なる政治レベルが協力し、互いの責任を尊重しあう」という価値観も、ドイツに次いで高く評価されている。
補完性の原則
スイス連邦は26の州(Kanton/canton)と2100超の基礎自治体(Gemeinde/commune)から成る。政治レベルは連邦、州、基礎自治体の3層構造だ。カナダや米国、ブラジルなど連邦制を採る他の国々と同じく、「補完性の原則」が適用される。
この原則は、連邦法と州法に違反しない限り、基礎自治体は域内の問題を自由に決定できることを意味する。基礎自治体では解決できない課題は州や連邦の政府が引き取る。州もまた、連邦法に違反しない範囲で自由を持つ。
基礎自治体は上位2層で地域の利益を代表し、州は連邦に対して域内の利益を代表する。
スイス連邦憲法には、各州が「連邦の意思の形成」に参与することが明記されている。ベルン大学のスイス政治学者、ラヘル・フライブルクハウス氏は論文で、州が自らの利益を国政に反映させようとするあまり「州によるロビイングが連邦憲法を損なう」ことがあると指摘した。
新型コロナ禍では「州の権限」という言葉が決まり文句のように使われた。ロックダウン(都市封鎖)などの感染対策は、州が独自に決定できる場面が多かった。北部バーゼルでは閉鎖された飲食店を横目に歩きながら、1時間も電車に乗ればベルンで陽気にグリューワインを飲む人々を見ることができた。
「州の過半数」
コロナ禍の2020年11月末、国民投票に歴史的出来事が起きた。スイスの多国籍企業に国外の人権侵害の責任を負わせる「企業責任イニシアチブ」が、「州の過半数」を得られず否決された。有権者の過半数の支持を得ながら州票で覆されたのは、1955年以来2回目だった。
国民が起草した連邦憲法改正案を国民投票にかける「イニシアチブ(国民発議)」や、議会を通過した連邦憲法改正案を国民投票にかける「強制レファレンダム(国民表決)」は、有権者の過半数に加え、州の過半数も可決要件になる(連邦憲法ではなく連邦法の改正について、有権者の署名を集めて投票にかける「任意のレファレンダム」は除く)。
19世紀まで、「国家連合」を結んでいたスイスはあらゆることを「州の過半数」で決めていた。州の過半数を得た意見が、スイス全体に関わる問題を決定していた。
1848年のスイス連邦建国以来、この「州の過半数」と、連邦議会の全州議会(上院)は、小規模州の利益を国政に反映させるための車の両輪となっている。

おすすめの記事
民主主義
全州議会
1848年以来、小規模州も大規模州と同数の議員を全州議会に送り込むことによって、その代表権が保障されてきた。二院制を採るスイスでは、議会のあらゆる決定は全州議会と国民議会(下院)双方の賛成を得なければならない。
全州議会は46議席あり、20州が2議席を、歴史的な理由で6準州は1議席を充てられている。全州議会は米国の上院をモデルにしている。

おすすめの記事
「姉妹共和国」だった米国とスイス
国家連合から連邦国家へ
1870年代以降、二つの少数派による抵抗運動が起きた。保守勢力と、フランス語圏の連邦推進派が議会動議やレファレンダムを通じ、連邦憲法の持つ価値観に異を唱え始めた。
政治学者のフェリックス・ブフリ氏とディーター・フライブルクハウス氏は、これを「連邦国家への基本的な賛意」を示した動きとみなす。これ以降、「国家連合」への揺り戻しは不発に終わっている。
第1次大戦後に生まれた連邦税は「暫定措置」
スイス連邦政府が所得や資産に対し税金を課すことができるようになったのは、建国から70年近く経った1915年になってのことだった。ただ、連邦による税の徴収は未だに「暫定措置」という扱いで、定期的に国民投票で延長の是非を問わなければならない。
直近2018年の国民投票では、連邦税の根拠法の延長が84.1%の圧倒的賛成多数で可決された。万が一否決されれば、連邦政府は歳入の半分以上を失うことになる。
今回の延長は2035年まで有効だ。つまり26州・4言語から成るスイスの有権者は10年後に再び、連邦政府の徴税権の是非を判断する。
編集:Mark Livingston、独語からの翻訳:ムートゥ朋子、校正:宇田薫

おすすめの記事
「政治家に任せっきり」にしない スイスの直接民主主義

JTI基準に準拠


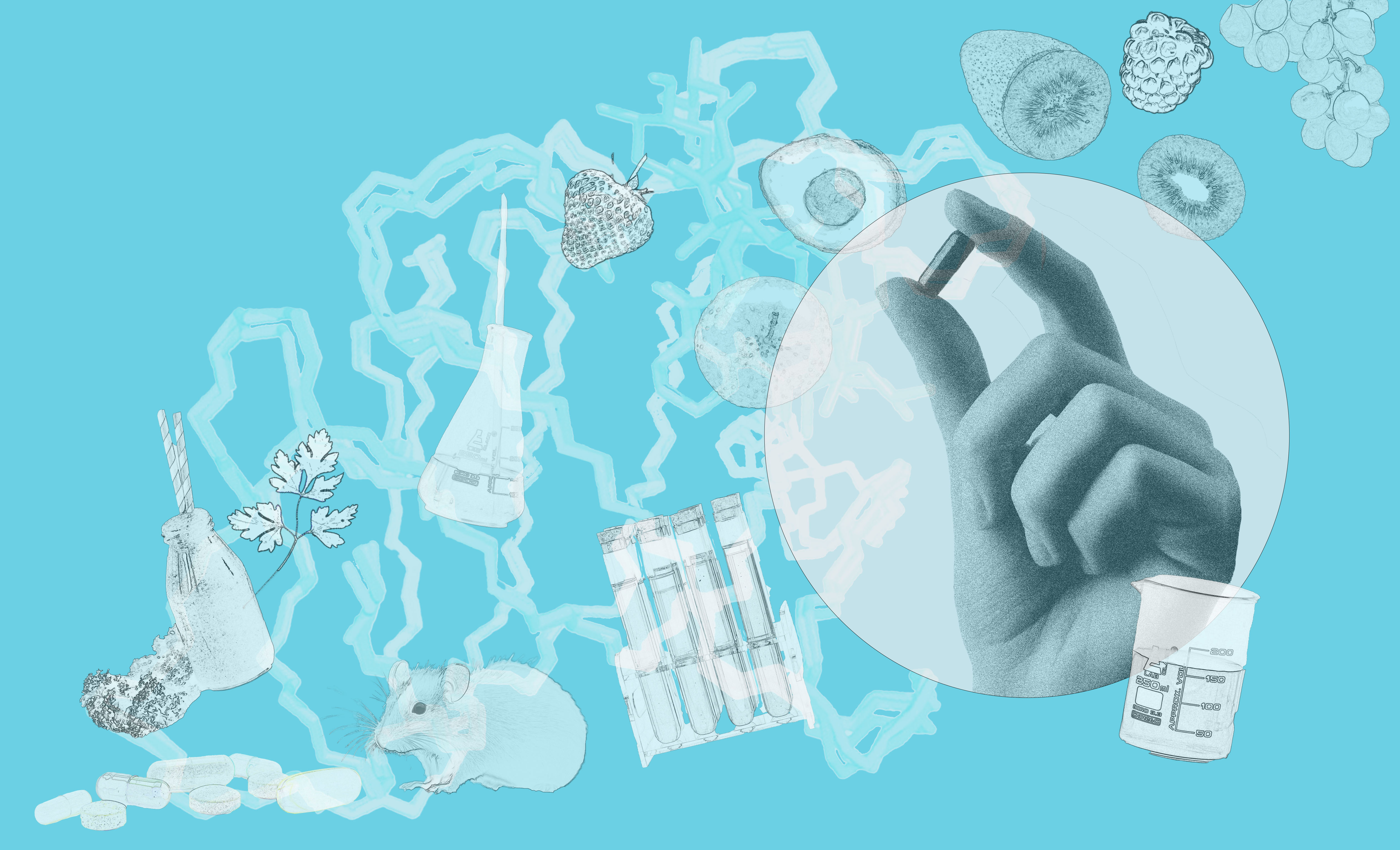







swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。