
連邦の課税権を握るスイス国民
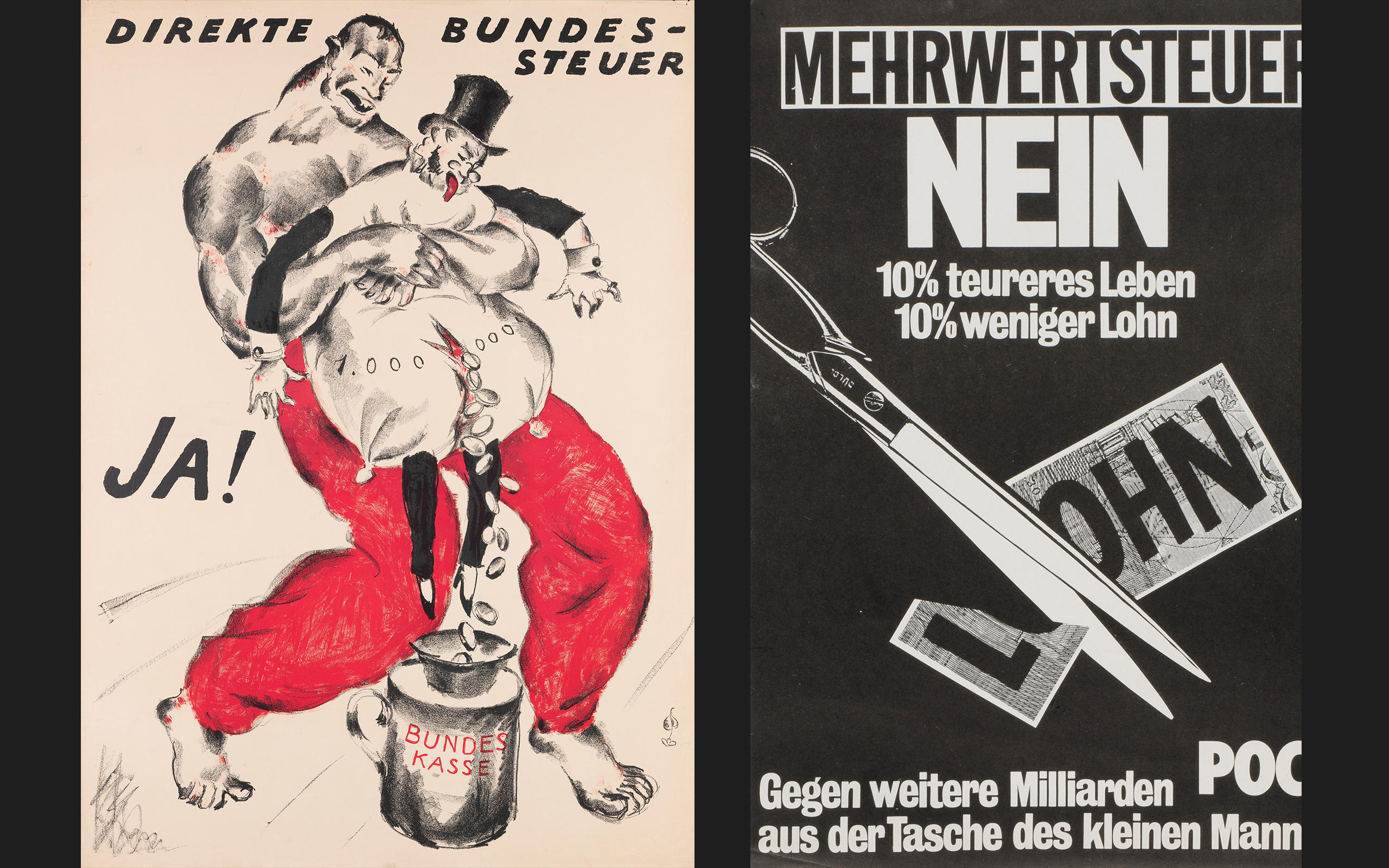
2018年3月4日、スイス国民は強制的レファレンダムで、連邦政府に引き続き2つの課税権を認めるかどうかに票を投じる。ともに重要な財源で、数百年にわたる連邦制と直接民主制の歴史の中で重要な意味を持つ投票となりそうだ。
国家が徴税の可否を逐一国民に問う。海外では驚かれるが、スイス人にとっては当たり前のことだ。税法や税率表までも国民が最終的な決定権を握る。国民主権はスイスの直接民主主義の中核を成す。
今回投票にかけられる「新財政規律2021」では直接連邦税と付加価値税(VAT)の延長の是非を問う。

現在、この2つの税金は連邦予算の歳入の3分の2を占める。課税が始まった当初から国民投票にかけることが定められており、今回で8回目の投票となる。
税の連邦制
スイス連邦が建国された1848年、直接税は州が徴税し、連邦予算は関税で成り立っていた。第1次大戦後、急拡大した連邦予算をまかないきれなくなり、連邦税の徴税が始まった。
1915年、有権者は16~17年限定の「戦争税」導入を賛成94%で可決した。このときから、直接税の課税権は州に、間接税は連邦に属すると言う原則から遠ざかっていくことになる。
その後も似たような税金が何度か導入された。戦況が深刻になり、連邦の担うべき課題が増えてきたためだ。税金はさまざまに命名され、賦課期間もそれぞれだった。その他の間接税も増えた。
延長は問えど
1958年、国民と州は直接連邦税とVATの徴税権を連邦に与える議案を可決した。期間限定の課税権で、その後も期限が迫るごとに延長の可否を問う国民投票が行われる。
これまで国民投票ではいずれも大幅に賛成が反対を上回った。前回2004年の投票では74%が賛成票を投じた。期限切れに追い込もうとする試みは毎回失敗しており、18年3月4日の国民投票でも期限延長が可決されるとみられる。

おすすめの記事
連邦の期限付き課税権 無風で延長のワケは?
(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)

JTI基準に準拠






















swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。