古材生かして大聖堂を修復 石工職人トーマスさん

北スイス・バーゼルにある大聖堂の塔の高さは65メートル。石工職人リシャード・トーマスさんは毎日2回、仮設リフトに乗り込んで塔の上まで登っていく。
赤褐色の砂岩でできた大聖堂は500年の月日と共に風雨に打たれ、石材の一部が崩れ落ちている。トーマスさんは3人の職人、見習いと共に、大掛かりな化粧直しをする。
宙ずり状態で塔を上り下りする仮設リフトには囲いがない。ガタガタと揺れながらリフトで上まで登っていくと、ライン川の流れとバーゼル市内が一望できる。
○ ○ ○
バーゼル大聖堂の築造は古く、8世紀代までさかのぼるという。917年にハンガリー人によって破壊され、12世紀に再び建立されたが、14世紀の地震で倒壊。現在のゴシック様式は16世紀に再建された。
トーマスさんのモットーは古材をできる限り生かすこと。
現在の修復技術で新しい石材に替えれば、大聖堂を70〜80年ほどもたせることは可能だ。「でも、それでは石材に刻まれた歴史の重みが失われてしまう。新しい石材に替える量をなるべく抑え、古い石材を生かして修復するよう努めている」と話す。
この修復方法だと、実際にもつのは30年程度という。「しかるべき時が来たら、また修復し直すだけさ」とトーマスさんは笑う。
○ ○ ○
石工職人は石の目利きも問われる。
修復不可能な箇所だけドイツの石切り職人に石材を加工してもらうのだが、石の良し悪しを選別できないと、その後の修復作業に大きく関わってくるからだ。
「ここで手を抜くと、次の世代が大変だろう」
現在のバーゼル大聖堂の修復作業は一世一代の大仕事だが、技や知識を見習いに伝えることにも心血をそそぐ。
「こうやって毎日大聖堂を間近に観察していると、昔の石工職人が一つ一つ慎重に積み上げていった技に頭が下がる思いと共に、同じ仕事をしていることに誇りを感じているよ。だから、修復の技を後進に伝えることも大切なことだ」と話している。
swissinfo ジュリー・ハント 安達聡子(あだちさとこ)意訳
バーゼル大聖堂:
バーゼル大聖堂の築造は8世紀代にさかのぼると言われる。
12世紀にロマネスク様式に再建されたが、14世紀の地震で倒壊。
16世紀に現在の壮大なゴシック様式に再建された。

JTI基準に準拠



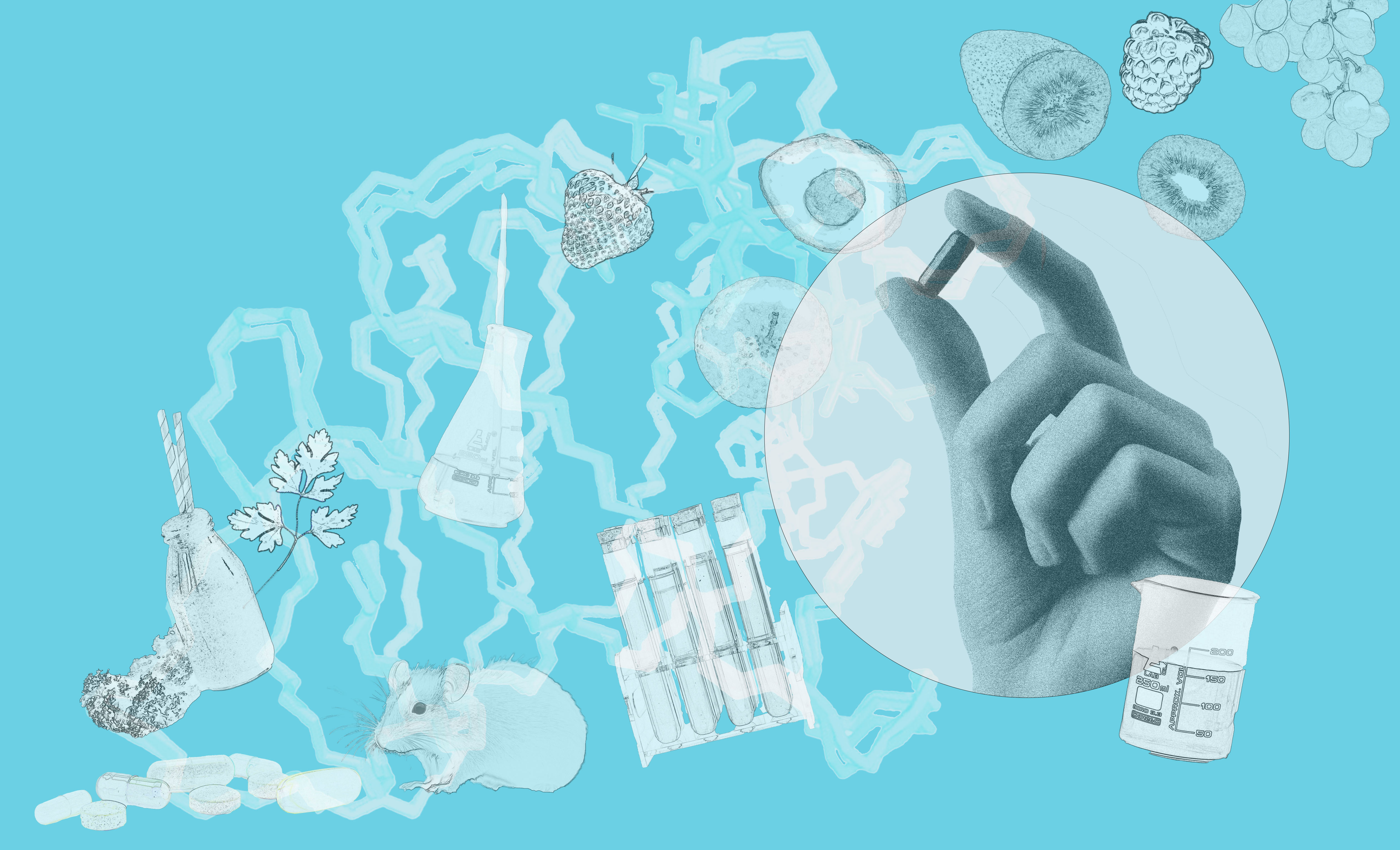





swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。