
天の川の秘密が明かされる
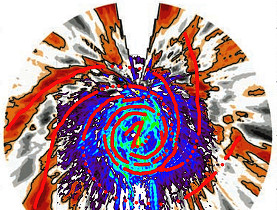
チューリヒ州立大学の研究者が参加している研究チームが、赤外線を使って天の川銀河の構造を解明した。
研究チームはこのほど、恒星、ガスの霧、塵 ( ちり ) の雲が渦を巻いている銀河系の全体像をとらえ、一般に公開した。この画期的な発見は、暗黒物質 ( ダークマター ) を追及する研究者にとっても、大きな助けになると考えられている。
はっきりと見えた銀河の姿
これまで、人類が住む太陽系がある銀河、「天の川銀河」の中心は、塵の雲が邪魔をして見えなかったが、衛星の助けを借り、赤外線を当てることで障害物である塵の雲のカーテンを開けたのである。こうして、星の配置やガスの流れを測定できるようになり、渦を巻く完璧な銀河系の地図が完成した。星が集中している2本の腕は銀河系の中心から伸び4本に分かれ、そのふちまで届いている。
銀河系にある星は、円盤状に散らばり、中心は棒のような形をしている。なぜ、腕が4本に分かれ銀河系の渦の軌道から離れているのかということも解明された。それは、渦の中心の引力に引かれるためだという。この画像が示すところによると、銀河系の核はこれまで思われてきた以上に左右対称であることも分かった。
暗黒物質の追求
チューリヒ大学理論物理学科の天文物理学者、ペーター・エングルマイヤー氏は、米アイオワ州のマーティン・ポール氏、ドイツのボーフム市ルール大学のニコライ・ビサンツ氏などと共同で今回、天の川銀河の全容を解明した。この画像を使いフランスの研究チームが、暗黒物体が何でできているかを究明することになっている。
「暗黒物質が壊れる際、ガンマ線を発するといわれています。そこで、研究者は天の川銀河を観察し、ガンマ線のある場所から暗黒物質の位置を確かめようとしています」
とエングルマイヤー氏は説明する。
「暗黒物質を研究する研究者が、暗黒物質から発生する自然物質を発見するためにわれわれの作った画像が利用されるのです」
太陽系がある天の川銀河は、宇宙にあるほかの星雲や銀河系の基本研究に適している。天の川銀河以外はあまりにも距離がありすぎるため、正確な観察が難しいからだ。われわれの住む銀河系を研究すれば、それ以外の銀河系の理解にも役立つという。
衝突軌道
一方、米スミソニアン大学の天文物理学科の研究では、天の川銀河はこれまで推定されていたより15%大きく、これを構成する物質も50%多いことが判明した。星と太陽系のさまざまな地点との距離を測定することで、銀河系の立体的な地図を作成することもできるようになった。
地球と太陽は時速100万キロ弱という猛スピードで銀河の中心を回っていることも分かった。これまでの考えられてきたスピードより時速16万キロ速い。ということは、天の川銀河は隣にあるアンドロメダ銀河により早い時期に衝突する可能性があるということでもある。とはいえ、衝突は早くとも20億年から30億年先のことだ。
swissinfo、マシュー・アレン 佐藤夕美 ( さとう ゆうみ ) 訳
国際天文年
今年は、国際天文協会とユネスコが中心となり「国際天文年」と定められ、130カ国が天文学に深く親しんでもらうことを目的にさまざまな催し物を予定している。
ちょうど400年前、ガリレオ・ガリレイが自分で望遠鏡を作り、天文観測をし始めた。ドイツ人のヨハネス・ケプラーも『新天文学』を執筆し惑星の運動に関する研究を発表した。
天の川銀河は何十億もあるといわれる銀河系の1つで、太陽系が含まれる。天の川銀河にある星は平均的に散らばり、棒渦巻状になり2本の腕が出ている。この2本はそれぞれ2つに分かれ4本になる。その中心は、大きなブラックホールになっていると考えられている。
地球がある太陽系は、天の川銀河のオリオンの腕の上にあり、その中心から2万5000光年の距離にある。
天の川銀河の隣には、アンドロメダ銀河がある。

JTI基準に準拠


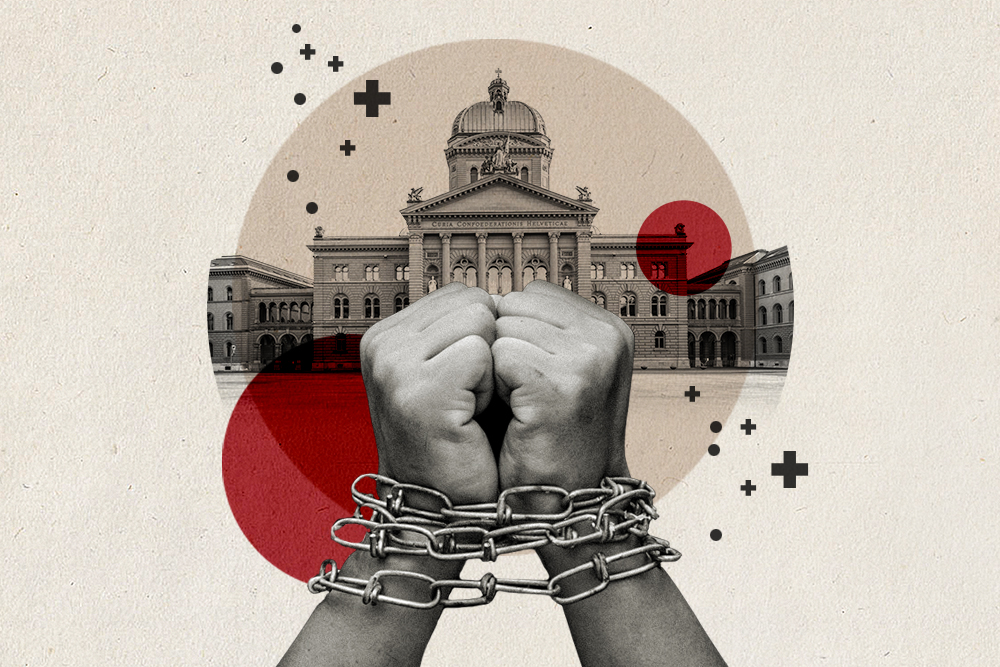






















swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。