
薬剤耐性に挑む世界 スイスはなぜ出遅れたのか
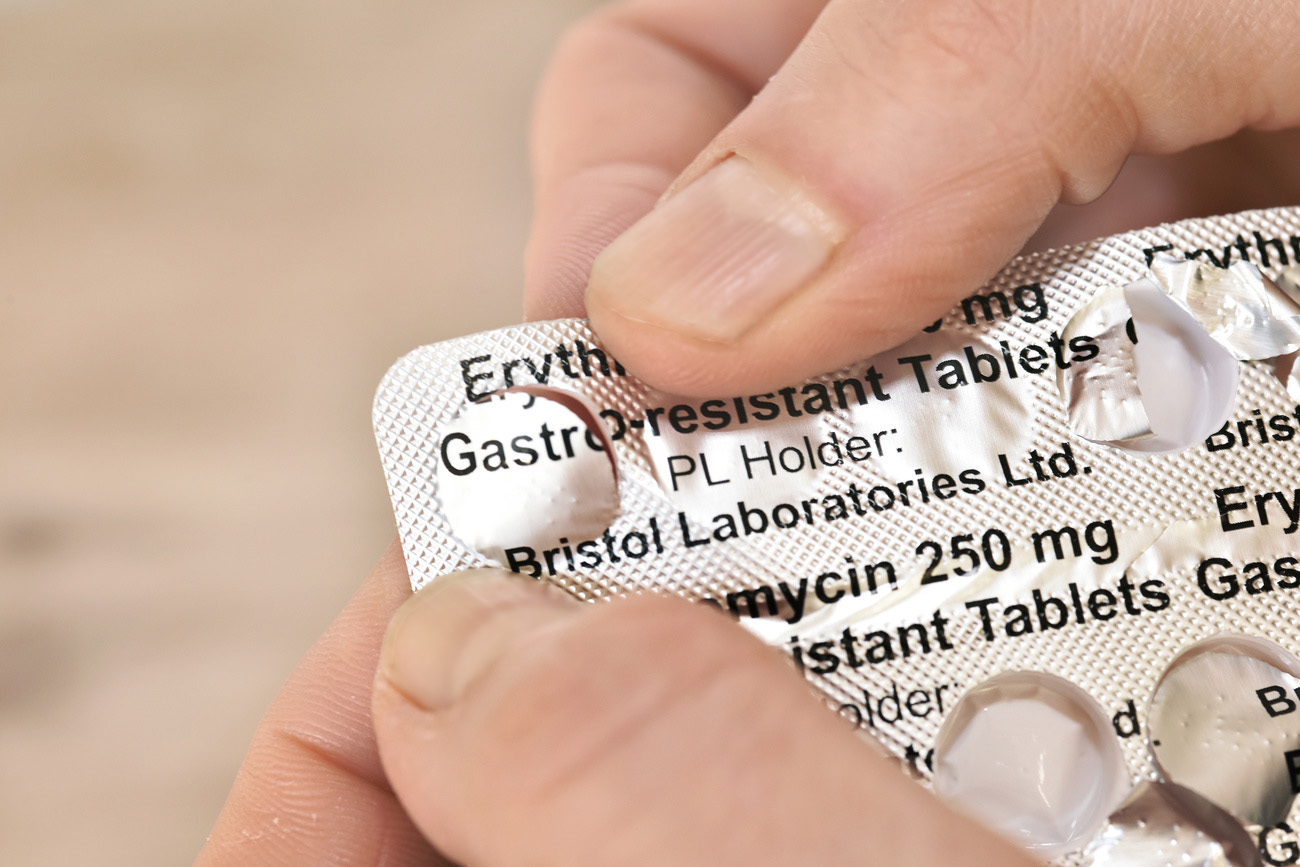
世界の薬剤耐性が深刻化するなか、収益性の低い抗菌薬を開発する企業は極めて少ない。英国、日本などが急ピッチで開発促進に乗り出す一方で、スイスは危機感が薄く対応が遅れている。

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
抗菌薬(抗生物質)が効かない薬剤耐性(AMR)は世界の水面下で静かに進行している。国際保健の専門家らは長い間、薬剤耐性はサイレントパンデミック(静かな世界的大流行)をもたらす深刻な危機であると警鐘を鳴らしてきた。薬剤耐性による2019年の世界の死亡者数は約130万人に上り(同年の死因3位)、このまま対策を講じなければ年間死亡者数は2050年までにがんによる死亡に匹敵する1千万人に達すると推定される外部リンク。
日本では、薬剤耐性菌の中で特に高頻度のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)とフルオロキノロン耐性大腸菌(FQREC)だけで年間約8千人が死亡し、その後も数は増えている(2019年報告書外部リンク)。特定の抗菌薬に耐性を持つ菌の割合である耐性率も依然高い外部リンク。
薬剤耐性菌の院内感染も度々起きている。2018年には鹿児島大学病院で入院患者5人から多剤耐性アシネトバクターが検出され、うち3人が死亡。静岡市立静岡病院でも感染者4人中2人が死亡した。
だが、新規抗菌薬の開発に着手する製薬企業は世界的にもごくわずかだ。抗菌薬は莫大な開発コストがかかる割に市場価格が低く、コスト回収が保証されないのがネックになっている。新薬開発には通常10〜15年、コストは10億ドル(約1470億円)を超えるが、抗菌薬は安価な上、薬剤耐性菌の出現を防ぐために適正な使用が求められる。
抗菌薬セフトビプロール(米商品名はzevtera)を開発したスイス・バイオテック企業バシレア(Basilea)のマーク・ジョーンズ国際関係部長は「抗菌薬は、どんなに革新的なものでもスナック菓子程度の安い値札しか付かない。しかも抗がん剤と異なり、よく効くものほど最終手段として薬棚の奥深くに保管される」と話す。
このため、小規模企業が開発した有望な新薬候補を買収し製品化する役割を担うことの多い製薬大手のほとんどが抗菌薬分野から撤退した。
米バイオ医薬品メーカーのアカオゲン(Achaogen、2002年創業)は、同社開発の抗菌薬プラゾマイシン(商品名はZemdri)が2018年に米国食品医薬品局(FDA)の承認を受けたが資金繰りでつまずき、同薬発売直後の2019年に破産申請した。
抗菌薬を化学構造の類似性などに基づきグループ分けしたものを抗菌薬クラスといい、13以上のクラスが定義されている。同じクラスの分子は似た機能を持つことが多く、耐性パターンも似ている可能性がある。
インセンティブを導入する国も
一部の国は具体的な対策を講じている。英国が導入したのは、ネットフリックス(Netflix)のようなサブスクリプション形式のプル型インセンティブだ。抗菌薬をどれだけ使ったかではなく、国民健康サービス(NHS)が固定額の年間利用料を製薬企業に支払う。2019年に試験的に導入後、企業のキャッシュフローが改善し患者の抗菌薬アクセスも向上したため、2024年5月から本運用が始まった。
日本は、抗菌薬を開発・販売する企業の収入が一定額に満たない場合に差額分を国が支援する収入保証形式のプル型インセンティブを導入している。厚生労働省主導の抗菌薬確保支援事業(2023年開始)で、これまでに塩野義製薬とファイザーが支援対象に選ばれた。
同省の担当者はスイスインフォの取材に対し、両社は①抗菌薬の適正使用を保ちつつ②新規抗菌薬の開発を促進し③耐性菌の治療の選択肢を確保するという同事業の目的に合致した成果を上げていると回答した。同事業の運用に関しては、日本の製薬業界団体である日本製薬工業協会が具体的な改善案の声明外部リンクを出すなど、業界も積極的に介入している。
スウェーデン、イタリア、カナダ、米国でもインセンティブの具体的な検討や導入が進む。

おすすめの記事
製薬大国スイスで薬不足が起こる理由
インセンティブとは行動を促進するための刺激や動機付けのこと。抗菌薬開発を促進するインセンティブには、薬の開発から承認までの研究開発を支援する「プッシュ型」と、薬の上市と販売事業を支援する「プル型」がある。
プッシュ型は公的資金による研究開発支援や税制優遇などがある。プル型は企業の収益を保証し安定的な販売を継続できるようにすることが目的で、薬の利用権に対して一定額を支払うサブスクリプション形式、一定の売上規模に満たない場合に差額を補填する収入保証形式などがある。
薬の承認に対する成功報酬、薬価の優遇、特許権の延長、事前買取りなどもプル型インセンティブに分類される。
危機感の薄いスイス
スイスにも薬剤耐性の脅威が忍び寄るが、当局の危機感は薄い。外国旅行や輸入食品は薬剤耐性を拡散する要因の1つであり、薬剤耐性の割合が比較的低いスイスにも、帰国・入国者の体内や輸入食品を通じた拡散の懸念が高まっている。
実際に薬剤耐性菌を持つ患者に対応する病院にとって、有効な抗菌薬が不足するリスクは現実的な脅威だ。
チューリヒ大学病院のシルビオ・ブルッガー医師は昨年、カルバペネム系抗菌薬に耐性を持つアシネトバクター・バウマニ(CRAB)に感染した熱傷患者(44)を治療した。ブルッガー氏は「私たちが体験した耐性菌のレベルは恐ろしいものだった。その細菌は鼻、肺、傷口などあらゆる場所に広がり、さらに血管内に侵入した。こうなると、治療しなければ感染により死亡する確率が非常に高くなる」と当時を振り返る。
CRABは病院内に瞬く間に広がる。特に熱傷病棟のような高湿度の環境ではなおさらだ。2007年にはスイス西部の熱傷病棟でCRABの院内感染外部リンクが発生し、消毒のために一時閉鎖された。
この特定のCRABに効いた抗菌薬はスルバクタム/デュロバクタム(商品名はXacduro)だけだった。同薬は2023年に米国当局が承認済みだが、スイスは未承認のためその都度輸入しなければならない。チューリヒ大学病院では同薬を非常に高額な値段で輸入し、患者の命を救った。
こうしたことが当たり前になりつつある状況にブルッガー氏は懸念を強める。「患者の治療に必要な抗菌薬がスイスで未承認なために輸入を強いられるケースが増えている」
製薬企業の中には、特に人口900万人程度のスイスのような小規模市場の国では大きな売り上げが望めないため、商品化を遅らせたり見送ったりするところもある。スイスの医薬品規制当局に承認を申請しないことすらある。
2010〜2019年に世界の主要市場に出た18種類の抗菌薬外部リンクのうちスイスで承認されているものはわずか6種類で、日本の5種類を1つ上回るに過ぎない。
一方、サプライチェーン(供給網)のボトルネック(停滞・低下)や製薬企業による市場からの薬の回収が増えるなか、既存の抗菌薬も入手困難になってきている。
ジュネーブ大学病院の薬剤師、ヤシン・ディフ氏によれば、同病院では2023〜2025年の間に88種類の抗菌薬の在庫切れの報告があった。欠品で影響を受ける細菌(感染源)は32種類に上る。抗菌薬の輸入を余儀なくされたケースは16件、スイス未承認または市場撤退により国内での入手が不可能だったケースは5件だった。
こうした対応には当然コストがかかる。輸入抗菌薬は通常価格の平均2.5倍、なかには5倍もの値段が付く場合もあるとディフ氏は言う。輸入による遅延は治療を妨げるだけでなく、病院の負担も増す。
裕福さがあだに
だがスイス当局の動きは緩慢だ。スイス連邦政府は少なくとも10年前から薬剤耐性に関する国の戦略(AMR戦略外部リンク)の一環として、新規抗菌薬開発のインセンティブについて議論しているが、スイス製薬企業のバシレア、バイオヴァーシス、ロシュはいずれも、他国から資金とインセンティブを受けている。
スイスインフォの取材に応じた医師らは、スイスでは薬剤耐性の割合が比較的低く、抗菌薬の適正使用に関する啓発活動が盛んで、抗菌薬が必要な場合には輸入できる余力があるため、薬剤耐性の危機感が伝わりにくいと語った。
ジュネーブ大学病院の感染症制御部門長のステファン・アーバース医師は「スイスは裕福だという強みがある。ほとんどの国では医師が薬剤師に費用を気にせず新しい薬の輸入を依頼することはできない」と言う。
だが製薬企業が新薬を開発できなければ、こうした対応もいずれできなくなる。
「これは単に当病院の患者に抗菌薬を届けるだけの問題ではない。富と製薬産業を抱えるスイスには、世界が抗菌薬を使い果たす事態を防ぐ責任がある」とアーバース氏は指摘する。
新規抗菌薬の開発支援を目的とする業界団体、AMRアクション・ファンド(AMR Action Fund)のヘンリー・スキンナー最高経営責任者(CEO)は「これは世界全体の問題だ。スイスのような高所得国は、適切な市場インセンティブを提供し、企業規模に関わらず製薬企業が抗菌薬の開発投資に見合うリターンを得て開発を継続できるように積極的に取り組むべきだ」と主張する。「販売して損をするなら誰も抗菌薬に投資しなくなる」
スイス連邦政府はこれまで、コストや薬剤耐性に対する他の措置があることを理由に、連邦議会からのプル型インセンティブに関する提案外部リンクに難色を示してきた。連邦内務省保健庁(BAG/OFSP)はスイスインフォの取材に対し、政府は今秋に感染症法改正案を議会に提出する予定であり、これにより抗菌薬の財政的インセンティブ導入の法的根拠が整備されると回答した。法施行は早くても2029年の見込みだという。
だが刻一刻と時間は過ぎている。抗菌薬開発を続ける数少ない製薬大手の1つであるロシュは今年5月、新しい抗菌薬ゾスラバルピン(zosurabalpin)が臨床試験の最終フェーズに移行したと発表した。ゾスラバルピンは、二重膜を持つため抗菌薬が浸透し難いことで知られるグラム陰性菌に有効な約50年ぶりの新薬であり、グラム陰性菌の中でも特に治療が難しいとされる前出のCRAB感染症に効く薬として有望視されている。
ロシュのグローバル・アクセス責任者のマイケル・オーベルライター氏は、ロシュは抗菌薬アクセス確保のためにある程度のリスクを取るつもりだが、革新的な進歩を持続するには裕福な国からのインセンティブが必要だと言う。
「インセンティブがなければ、企業は市場から撤退するか、最初から参入しなくなる。さらに、既に始まっている当該分野からの『頭脳流出』、つまり研究者が他分野に移る現象を加速させるだろう」と同氏は懸念する。「一旦そうなれば、元の状態に戻すまでには長い年月がかかる」
編集:Virginie Mangin/sb、追加取材:ムートゥ朋子、英語からの翻訳・追加取材:佐藤寛子、校正:宇田薫

JTI基準に準拠




















swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。