
「ドローン攻撃は民間被害を減らす」は本当か

ドローン(無人機)の軍事利用が世界で広がるなか、「ドローン攻撃は精度が高く民間人の巻き添え被害を減らす」という神話が揺らいでいる。国際法の縛りが効かないことや、AI(人工知能)搭載ドローンの「殺人ロボット」化に対する懸念も強まっている。

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
ドローン攻撃を支持する人たちは、ピンポイントで標的を殺害できることを利点に挙げ、巻き添えの少ない「クリーンな戦争」が可能になると標榜する。だが民間の犠牲が世界で増えるにつれ、その信憑性や国際法の妥当性に疑念が向けられている。
英調査団体ドローン・ウォーズUKは、ドローンは武力行使の敷居を下げ、いわゆる「標的殺害(司法手続きを経ずに特定の人物を殺害する行為)」を拡大させるほか、説明責任の低下も招くと指摘する。

同団体の報告書外部リンク(3月公表)によると、近年ドローンの軍事利用が急増しているアフリカでは2021年11月〜2024年11月、50件のドローン攻撃により、民間人943人が死亡した。国別ではエチオピアが490人で最も多く、残りはブルキナファソ、マリ、ソマリア、ナイジェリア、スーダンだ。
共同執筆者のコラ・モリス氏は、標的を厳格な基準で絞り込んでいない様子があると指摘する。特定の人物というより「地域全体」に対して激しいドローン攻撃が展開され、「民間人と戦闘員の区別がほとんどなされていない」という。「例えばエチオピアでは、(当時武力衝突が激化していた)アムハラ州とティグレ州で犠牲者が多かった」
ほんの数年前まで、ドローン攻撃の大半は米国の対テロ作戦関連だった。対立や批判、法的論争の焦点は、パキスタンなど米国と交戦していない国で司法外殺人を実行する判断の是非だった。
しかし今、ドローンは国家間戦争と内戦の両方で幅広く使われ、50カ国近くが戦地投入している。低コストで高い効果を発揮する兵器だが、国際人道法の整備が追いつかず、軍備管理の規範がむしばまれる恐れもある。ドローン攻撃を原因とする民間人の死者は、累計で数十万人に上っている。
各国に広まった理由
ドローンが世界に拡散している理由は、安さと利便性だ。かつて中高度長時間滞空(MALE)ドローンを持つ国は米国、英国、イスラエル、中国に限られていたが、今はトルコとイランが既製部品とモジュール設計、オープンソース技術を最大限に活用し、安価で輸出している。
そして、多くの国の政府がこれを機に軍備を近代化している。ドローンは高価値目標を破壊する力を持ちながら、爆撃機や戦車の1000分の1の調達コストで済む。

ウクライナは6月、「クモの巣作戦」と名付けた大規模攻撃をロシアで実施し、ドローンの潜在力の高さを見せつけた。安価な一人称視点(FPV)ドローン100機余りでロシアの軍事基地4カ所の戦闘機計40機を破壊するという戦果を上げた。米シンクタンク、戦略国際問題研究所によると、ドローンの価格は1機当たり600〜1000ドル(約9万〜14万円)程度だ。

また、ドローンは国家対テロ組織などのいわゆる「非対称戦争」でも常套手段になった。デンマーク国際問題研究所(DIIS)によると、65を超える非国家武装集団がドローンを保有する。

国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチ(HRW)のベルキス・ウィレ危機・紛争・兵器局副局長は「パラダイムシフト(根本的な変化)」が起きていると指摘する。
一般向けに販売されているドローンは簡単に攻撃用に改造できるため、予算の少ない組織(あるいは3Dプリンターと米アマゾンのアカウントを持つ個人)でも都市部の標的を爆撃できる。
ウィレ氏は「今は安く、高い精度で民間人を狙える」と語る。
同氏が6月に公開した報告外部リンクによると、ロシアのドローン操縦者は一般向けのクアッドコプターを使い、ウクライナ南部ヘルソン州で自転車に乗ったり、道を歩いたり、バスに乗ったりしている民間人を追跡、爆発物を投下した。
国際人道法は時代遅れ?
ジュネーブ諸条約と追加議定書は無差別攻撃を禁止し、民間人を保護するよう明確に定めている。ただし、赤十字国際委員会(ICRC)は、交戦当事者が「区別」「均衡性」「予防措置」の各原則に従っている限り、ドローン攻撃そのものは国際人道法違反ではない、と指摘する。
ジュネーブ国際人道法・人権アカデミーの研究者、アナ・ロザリー・グレイプル氏は、国際人道法の厳格な見地からは「ドローンを遠隔操作し、標的を判断する人物は、その場の具体的状況に区別、均衡性、予防措置の各原則を適用するといった国際人道法の順守が義務付けられる」と説明する。
ウィレ氏の見方も同じだ。「法に問題はない。ドローンはただの運搬メカニズムだ。執行が問題なのだ」と話す。
同氏によれば、ドローンが危険なのは既存の法的枠組みに当てはまらないからではない。より効率的に、しかも違反者を特定しにくい形で、民間人を故意に狙うなどの違反行為を可能にするからだという。

自律型のAIドローンが「殺人ロボット」に
ウィレ氏によれば、こうした傾向はドローン運用システムの自律化で加速する恐れがある。なかでも懸念されるのが、AIの搭載だ。AIで能力を増したドローンが戦場を跋扈する日はそう遠くないかもしれない。同氏は「戦場の殺人ロボットには、さまざまな形があり得る。その1つがドローンだ」と指摘する。
ロシアとウクライナでは、ドローン技術とドローンへの対抗技術が急速に進歩している。
その1つがドローンの拡散に対抗するジャミング技術だ。ジャミングは意図的に高周波信号を発したり、電波障害を引き起こしたりして、ドローンのシステムを混乱、遮断、上書きする。
さらに一部の軍はジャミング対策として、離陸後に操縦者との通信が不要な自律型ドローンシステムの開発を推進している。何十万枚もの戦車の画像でAIに学習させれば、ドローンに自力で標的を破壊させられる。
ウィレ氏は「そうなれば、AIドローンは『殺人ロボット』の領域に入る可能性がある。人間が決定に一切介在しないからだ」と話す。「この種のドローンシステムでは、訓練の仕方によって子どもを殺すような学習がなされる恐れもある。そうなれば、ドローンは戦車を破壊するのと同じように、苦もなく殺害を実行するだろう」と警告する。
赤十字国際委員会もドローンの進歩を注視している。国際人道法上の課題をまとめた2024年の報告書では「(ドローンは)近い将来、ソフトウエアの更新や軍事ドクトリン(原理原則)の変更だけで簡単に自律型兵器システム、すなわち人間が介在せずに標的を選択し、武力を行使する兵器システムになり得る」と警告した。
国際法のグレーゾーン
国際人道法は戦争当事者が守るべき原則として、戦闘員と民間人を区別することや、攻撃で得られる軍事的優位に比べ、攻撃から生じる民間の犠牲が過大にならないようにすること、民間の犠牲を最小限にとどめるため予防措置を取ることを定めている。しかし、複雑な環境でのドローン使用が増えることで、合法的な標的を正確に識別することや、民間に被害が生じるリスクを評価することは難しくなる。
グレイプル氏は、AIによるデータ収集、またドローンが収集したデータをAIを使って分析し、その結果を軍の意思決定者に提供する仕組みには課題があると指摘する。「AIに組み込まれた偏見や思い込みがどう作用するのかを詳しく理解せず、その情報を元に人間が法的評価を行う場合、使い方次第で大きな問題が生じかねない」
ウィレ氏はまた、軍は国際人道法を「理解」したうえでドローンを配備するが、多くの場合、米国のIT企業など民間の商業主体にはそうした理解がないと警告している。
管理は弱く、規制は継ぎはぎ
モリス氏は「ミサイル技術管理レジーム(MTCR)」「武器貿易条約(ATT)」「ワッセナー協約」など今の兵器管理の国際体制には欠陥があり、ドローンの世界的な拡散や不正な使用を抑制できていないと警告する。
「ドローンの拡散と使用を規制するための国際連携が喫緊に必要だ。現在の規制枠組みは、明らかに適当ではない」
米ニューヨークで開かれる国連総会や、ジュネーブで開かれる関連会合では、いわゆる「殺人ロボット」などの自律型兵器が主要議題となっている。
ポルトガルが主導する加盟21カ国のグループは2024年3月、武装ドローンに関する透明性と説明責任の向上を呼びかけた。アントニオ・グテレス事務総長も加盟各国に対し、2026年までに自立型兵器を規制または禁止するよう強く促している。
グレイプル氏は「AIシステムで動くドローンは、標的の発見だけでなく選定や攻撃にまで、人間の介入なしで利用されかねないという問題を抱えている。明確な限度と規制が本当に必要とされている」と話している。
編集:Virginie Mangin/ac、日本語からの翻訳:高取芳彦、校正:宇田薫

JTI基準に準拠


















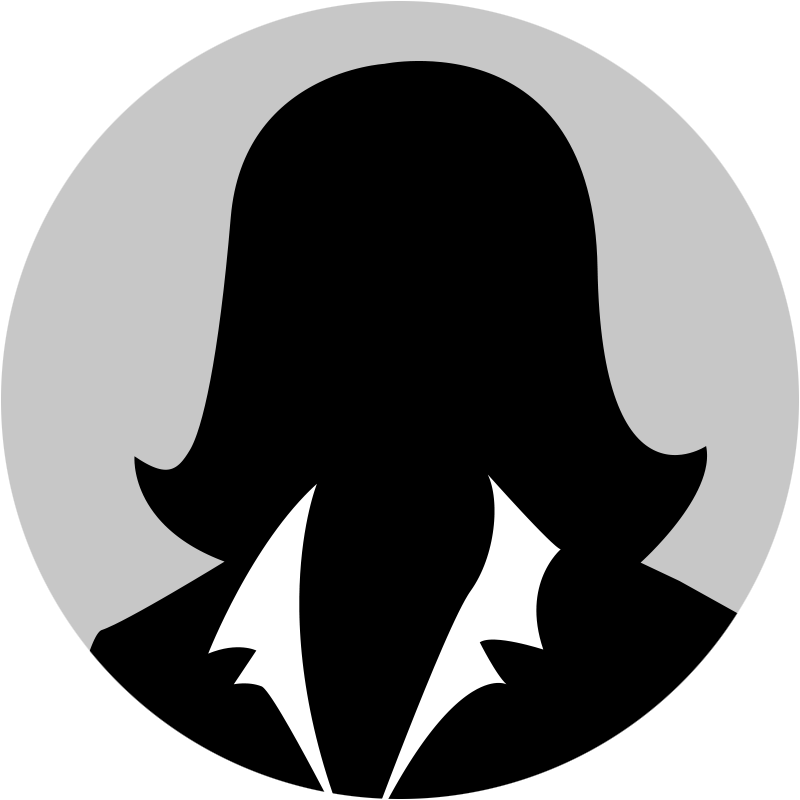
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。