
スイスは「汚れた金」と闘い続けられるか

少数の権力者が国家の金を横領し、私服を肥やす「クレプトクラシー」。スイスなど世界各国が対策に力を入れるなか、「汚れたカネ」撲滅を率いてきた米国の姿勢が軟化し、新たな課題を突きつけている。

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
クレプトクラシーが横行するナイジェリアでは、病院の人手不足が深刻化し、患者が適切な治療を受けられないと、アフリカ環境経済正義ネットワーク(ANEEJ)のエグゼクティブ・ディレクター、デイビッド・ウゴロール氏は語る。教室修繕費が不足し学校に通えない子どもが増え、修繕されない道路は交通事故のリスクを高める。
ナイジェリアのケースは「単なる汚職を超えている。国家の乗っ取り(state capture)だ」とウゴロール氏は言う。それが意味するのは、腐敗したエリートたちが資金を盗むだけでなく、法律をねじ曲げて権力を維持しているということだ。「そしてそれが、国の不平等と貧困をさらに強めている」
国連の推計によれば、アフリカから腐敗公職者や犯罪者が国外に不正に流出させる資金は毎年約900億ドル(約13兆5000億円)に上る。流出元の国々では公的医療への投資が半減し、教育への支出は4分の1減少する場合もある。
欧米諸国のなかには、自国の銀行に関するスキャンダルを受け、外国の汚職政治家の保有口座を対象とする動きも出ている。スイスはこれまでに20億ドル以上の不正資金を返還した。欧州連合(EU)は2024年、加盟27カ国で不正資産を回収するための新たな指令を採択した。
だが、それはほんの一部分にすぎない。ドイツ拠点の市民フォーラム・フォー・アセット・リカバリー(CiFAR)ディレクター、ジャクソン・オールドフィールド氏は「開発途上国から流出して個人の手に渡る資金の方が、返還される資金よりも依然としてはるかに多い」と言う。
強力な対応を求める声がある一方、欧米諸国がクレプトクラシー撲滅の優先度を下げていると指摘する声もある。この分野を主導してきた米国が関与を縮小し、こうした懸念をさらに強めている。
「間違ったメッセージ」
ドナルド・トランプ米大統領は2期目就任直後、米司法省が不正資金対策のため立ち上げた「クレプトクラシー・アセット・リカバリー・イニシアチブ」を解体した。
また、米国の企業や個人が米国外の公務員に対して不正な目的で贈賄を行うことを禁止する海外腐敗行為防止法(FCPA)の執行を一時停止した(現在は解除)。経済協力開発機構(OECD)の贈賄作業部会の会合も欠席した。
「米国は間違ったメッセージを送っている。アフリカ諸国の腐敗した政府を助長している」とウゴロール氏は言う。「この問題を国際的な議題に押し上げるために私たちがどれほど苦労してきたかを思うと、本当に残念だ」
これまでの成果は容易に得られたものではない。国連腐敗防止条約(UNCAC)で「資産返還」が主要項目に盛り込まれたのは2004年のことだ。また2017年には、米国と英国が共催したグローバル資産回収フォーラム(GFAR)で、盗まれた資金の返還原則が採択された。
先駆者から批判の的へ
スイス連邦外務省はスイスインフォの取材に対し、スイスは過去10年間、国際的な情報交換を促進するなど主導的な役割を果たしてきたと語った。
不正資金の集まる国とのイメージを払拭すべく、スイスはこれまで数十億フランを返還してきた。1986年にはフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領の銀行口座を世界で初めて予防凍結し、その後、マネーロンダリング(資金洗浄)法を改正した。また2016年までに、外国の不正資産返還に関する法律を導入した。
最も代表的なケースは2018年、1990年代にナイジェリアの政権を率いたサニ・アバチャ元大統領とその家族が盗んだ資金の一部、3億2100万ドルを同国へ返還したことだ。このケースでは初めて、市民団体が返還資金の使途を決定・監督するプロセスに関与した。ANEEJなど200以上のNGOが、貧困層に資金が行き渡るよう使途を監視した。
「これは成功だった。ナイジェリアに返還された資金の使途を、初めて受益者までたどることができた」とウゴロール氏は語る。「プロセスは円滑に進み、この方式は次第に標準になりつつある」
同様のアプローチで、ウズベキスタンに3億1300万ドルが返還された。返還資金の一部は産科病棟の改修に充てられた。
それでも、スイスの資産回収実績は完璧ではない。 アバチャ資金の初期段階では、送金した7億ドルの大部分が行方不明になったと報じられている。2022年の連邦監査では、スイスの制度に弱点があることが指摘された。監査局は、2016年の法律はあまりにも限定的で、実務で適用するのが困難だと指摘した。
プロセスも遅い。フィリピンのマルコス資金6億8300万フランは、60件の裁判を経て18年後にようやく返還された。スイス連邦政府は、その後の立法改正で手続きを加速させたとしている。
監査局はまた、単一の事例記録簿がなく、透明性が欠如していると指摘する。マネーロンダリング対策を専門とする国際機関、金融活動作業部会(FATF)は、資産回収の改善には「包括的な統計」を維持することが不可欠だとしている。
スイス連邦外務省はスイスインフォに対し、中央集権的な記録は存在しないものの(複数の州および連邦機関が関与しているため)、政府は監査局の他の勧告の一部にはすでに対応済みだと説明した。また、スイスは国連薬物犯罪事務所(UNODC)やその盗難資産回収プログラム(StAR)などの機関との「戦略的パートナーシップの強化」にも取り組んでいると述べた。
StARは、世界全体で計560件の事例から得られた約170億ドル相当の不正資産に関する記録をデータベースに記録している。しかし、このデータは氷山の一角に過ぎず、ある推計によると、世界の不正資金のうち押収されているのはわずか1%未満に過ぎない。

おすすめの記事
資産隠しの重大スキャンダル スイスの過去と現在
予防策の弱さ
CiFARのオールドフィールド氏は、銀行秘密や受益者情報の開示に対する意識が高まっているとはいえ、富裕国全体で「予防策の弱さ」が課題だと指摘する。
「欧州を含め、いまだに秘密主義的な法域が数多く存在する。そこではペーパーカンパニーを設立し、隠れ蓑にすることが簡単にできる」という。
スイス連邦議会は現在、企業の最終受益者を登録するための連邦レベルの台帳の設置や、法務アドバイザーに対するデューデリジェンス(適正手続き)義務の導入など、より厳格な措置を検討している。しかし、トランスペアレンシー・インターナショナルのスイス支部は、これらは依然、国際基準を満たさないと訴える。

おすすめの記事
外交
資金返還は「彼らの権利」
スイスなど各国による資産回収は遅々として進まず、先導していた米国は態度を軟化させた。ウゴロール氏は「不正資金の流れへの対策をめぐる政治的動向」が弱まっていると警告する。同氏の出身国ナイジェリアは、スイス、米国、英国の過去の政権の恩恵を受け、30億ドル以上を回収したが、盗まれた金額と比較すれば「ごくわずかな金額だ」という。
ナイジェリア国内の状況は深刻だ。同国はトランスペアレンシー・インターナショナルの2024年汚職指数で180カ国中140位にランクされている。人口の約40%が貧困層とみなされている。
「不正資金の返還は慈善事業ではない」とウゴロール氏は訴える。不正資金を取り戻すのは、「その国に住む人たちの権利だ」。
編集:Tony Barrett/vm/ts、英語からの翻訳:宇田薫、校正:大野瑠衣子
おすすめの記事

JTI基準に準拠


















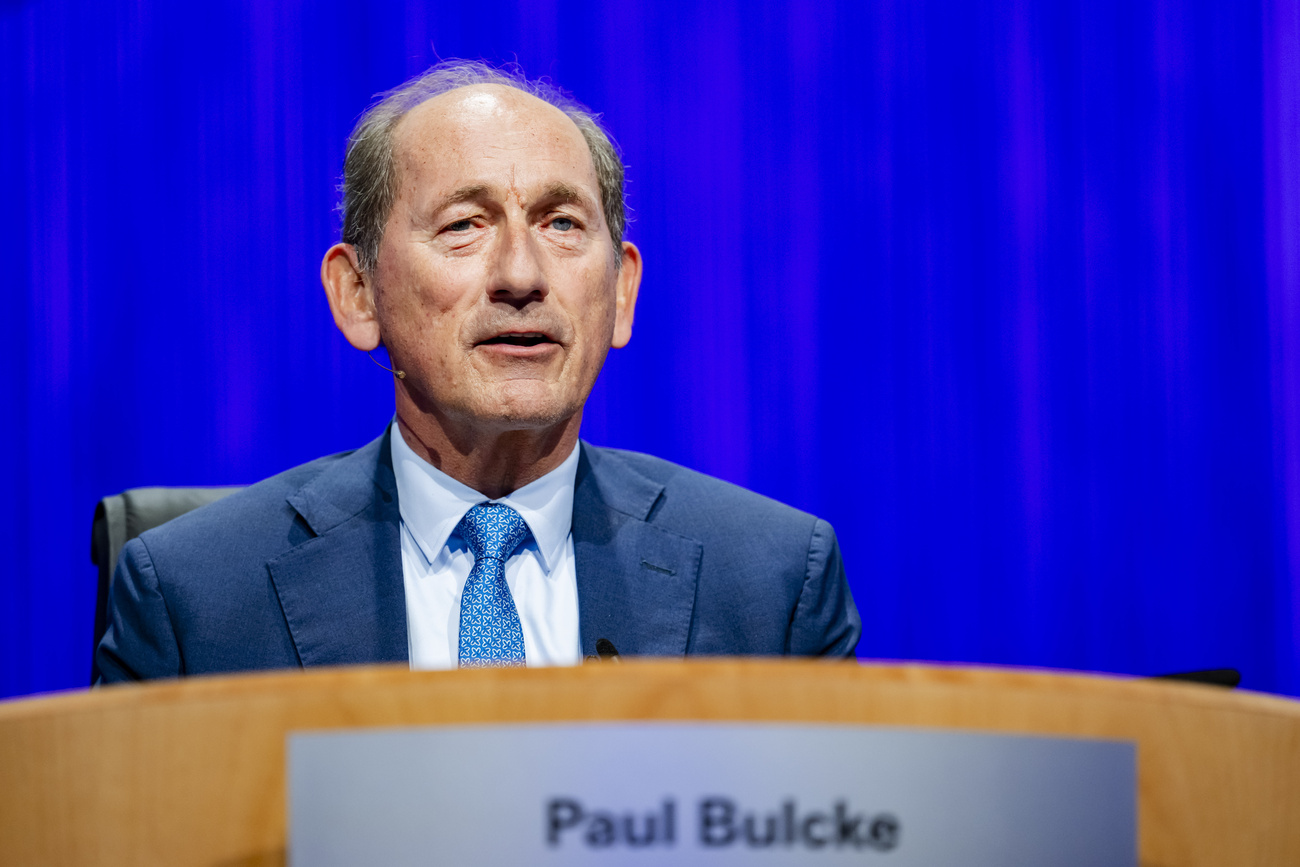


swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。