
バーゼルに生きる虫の世界
バーゼル自然史博物館には世界最大規模の昆虫コレクション外部リンクがある。それに限らず、ライン川沿いのこの町の人々は、生息する虫たちと空間を共有してきた。バーゼル出身の写真家アドリアン・キュンツリもその一人で、この土地に暮らす虫を観察し、写真に収めた。
その写真を撮るために遠出は不要だ。キュンツリは片手間にシャッターを切るのみで、家を出る必要すらなかった。この写真集外部リンクに登場する虫たちは全て、キュンツリを追ってきたか道ばたで這っていたものだ。被写体を見つけたのはリビングの窓や台所、地下、庭といった身近な場所。カマキリだけは例外で、スペインの休暇から帰ってきた荷物のなかに、卵でいっぱいの繭が潜んでいたのだ。
これら昆虫やクモ類を観察しているうちに、人々は異世界に引き込まれていく。キュンツリ宅のバルコニーに迷い込んだスズメバチに赤い頭のアリが群がる様子は、魅惑的な美しさを醸し出している。
近すぎる視点は時に見る者の目を惑わす。キュンツリは複数の写真を組み合わせて1枚の作品を完成させる技法も使った。画像編集ソフト・フォトショップの力を借りて、ぼかしに隠れていた被写体に輪郭を与えた。独特のぼかしと彩度で写真を非現実的なものに見せる一方で、極薄のはねや足に生えた繊毛をくっきりと写し出し昆虫の性質を詳細に捉えた。
いたるところに昆虫
アドリアン・キュンツリがマクロの世界に飛び込んだのは、たまたま新しいレンズを購入したのがきっかけだった。「突如、自分が虫たちに囲まれていることに気づいた。窓枠にもテーブル・庭のしおれた花にも。息子の水遊び用プールに放置され温まった水に、羽の生えたアリが群がっていたことがある」
地下室の窓に近い天井の隅にはクモの巣が張り、ひっきりなしに新しい虫が捕えられていた。キュンツリはそれらに「Y」と名付けて写真を撮り続けたが、ある日パタリと巣ごと消えてしまった。キュンツリの相方が地下室を掃除し、次なる被写体は掃除機に吸い込まれてしまったのだ。
(独語からの翻訳・ムートゥ朋子)
























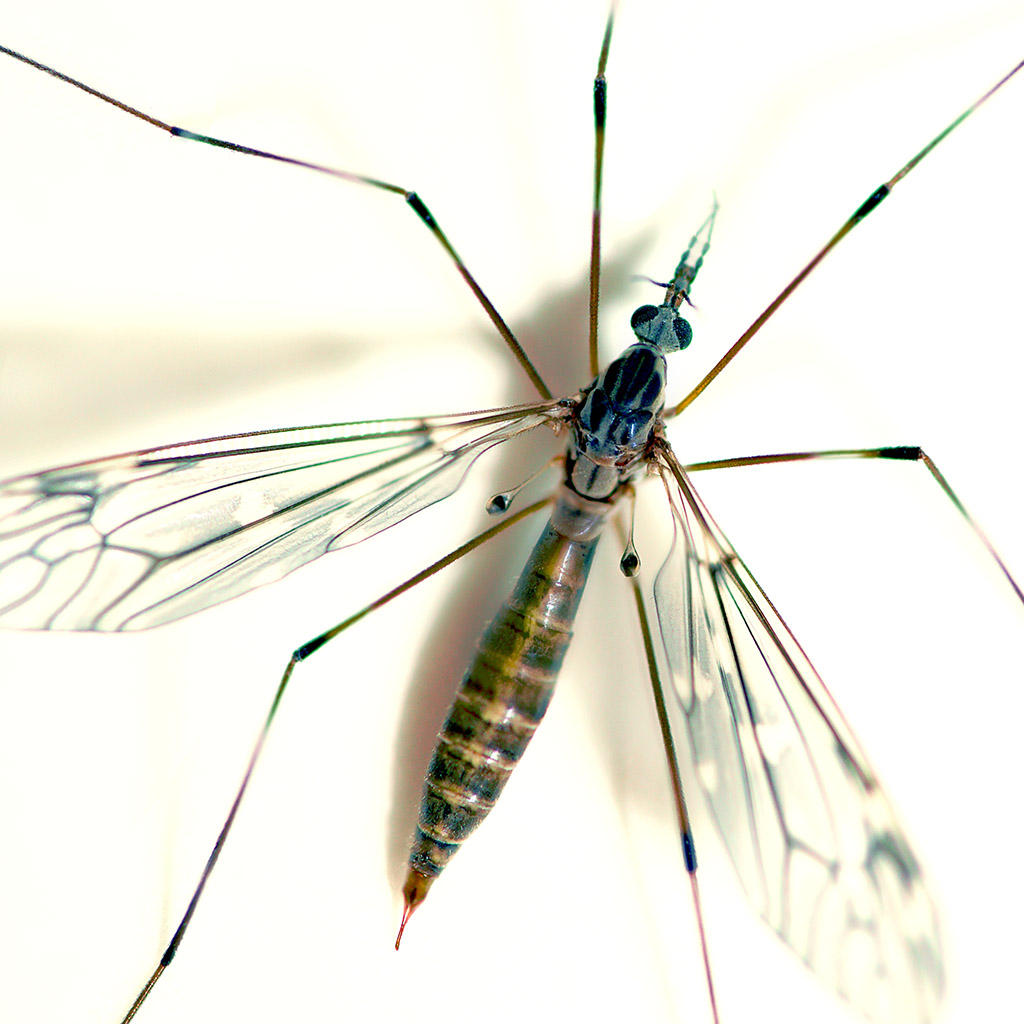









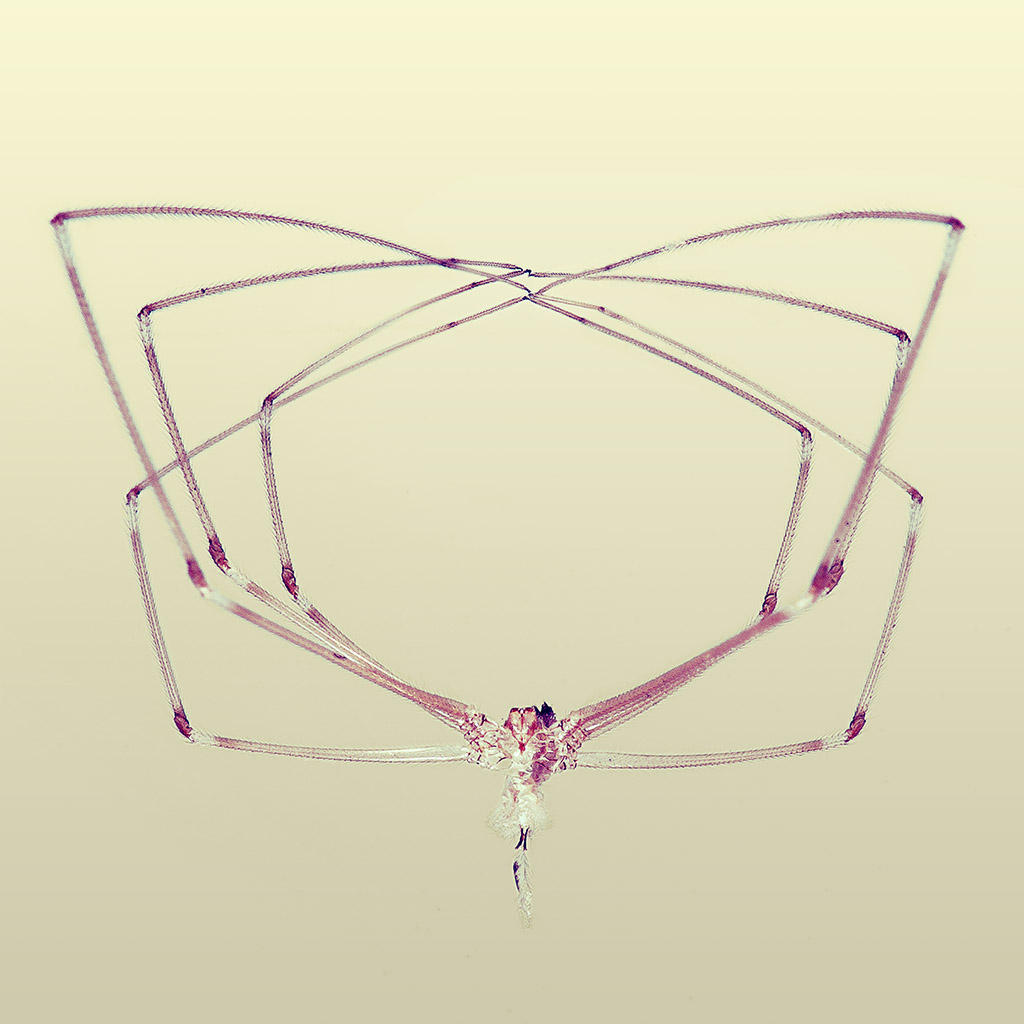




swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。