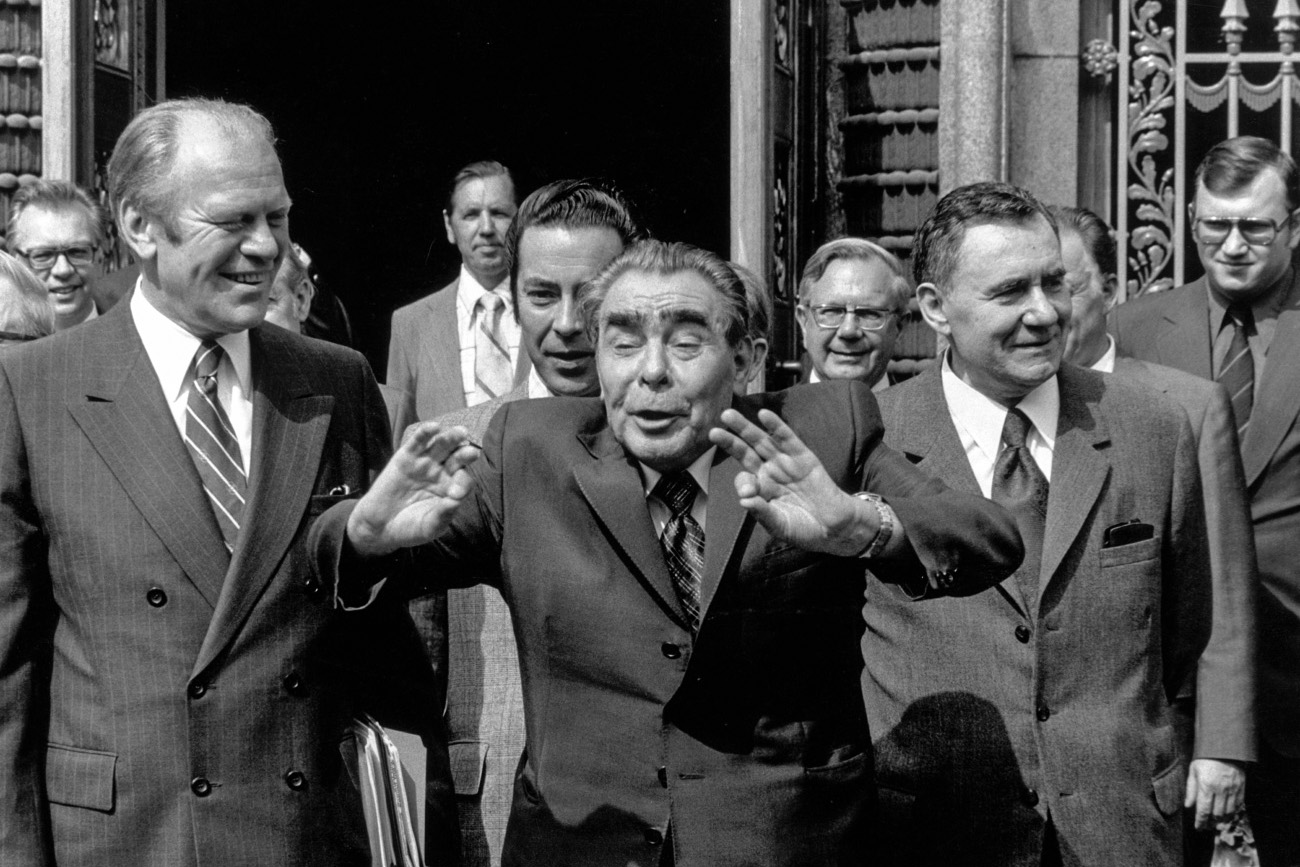
相互関税、参政党、外国人差別…スイスのメディアが報じた日本のニュース

スイスの主要報道機関が先週(7月22日~27日)伝えた日本関連のニュースから、①対日相互関税、15%で合意②参政党・神谷氏の成功③「安っぽい誉め言葉」の裏にある外国人差別、の3件を要約して紹介します。
日米相互関税の合意は、スイスと経済関係の深い欧州連合(EU)でも交渉期限が迫っていたこともあり、スイスの各言語圏で大きく報じられました。また20日の参院選で外国人排他政策を掲げた参政党が大勝した余波で、日本人の外国人との向き合い方にも注目が集まっています。
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録はこちら
対日相互関税、15%で合意は「良いディール」
日米両政府は22日、米国が日本に課す「相互関税」を15%に引き下げることで合意しました。4月に発表された当初税率の25%から大きく下がり、既に25%関税が発動していた自動車も引き下げられることに。スイスでは、日本の成功例に欧州連合(EU)も続くか、という視点の報道が目立つなか、日本経済への影響を深堀りした記事もいくつか見られました。
ドイツ語圏のスイス公共放送(SRF)の日本特派員マルティン・フリッツ記者は、合意は日本にとって「良いディール(取引)」だと解説。日本は交渉を始めたころこそもっと良い条件を目指していたものの、トランプ氏相手にそれは不可能だとすぐに悟り、「この状況で最大の条件を引き出した」と指摘しました。
フリッツ氏は「日本の自動車メーカーは、15%の関税でも耐えられる」と分析。鉄鋼関税が25%で据え置かれたことも、対米輸出が少ない日本にとっては対処できる範囲だとしています。
ドイツ語圏の経済紙フィナンツ・ウント・ヴィアトシャフトには、東京在住のフリージャーナリスト、ウルス・シェットリ氏の分析が掲載されました。「他の国に比べ日本はうまく立ち回っているが、トランプ氏の期待通りに貿易赤字が縮小するとは限らない」と指摘しています。
「うまく立ち回っている」というのは、日本の自動車産業が既に米国で生産していること、日本が米国にとって第2位の債権国で在日米軍基地にも寛大な支援を投じていることから「特別扱い」されている点です。15%で落ち着いたことは「少なくとも東京証券取引所の株価の急上昇が示すように、それだけの価値がある」とみています。
関税引き下げの見返りとして日本は5500億ドルの対米投資を約束しており、「日本は主要債権国としての実績から外れることはない」。短期的には貿易戦争を回避できるとの見通しを示しつつ、「米国の巨額の対日貿易赤字を本当に大幅削減できるかどうかは、深刻な疑念がある」と指摘します。
「その理由は、日本市場における外国製品・サービスに対する固有の障壁にある。これらは規制問題や対外貿易政策とは無関係で、日本の社会や文化そのものに深く根ざしている」。シェットリ氏はこう指摘したうえで、「日本人が品質と伝統に高い価値を置いている」ために米国製のコメや自動車の輸入量が増えないのだと分析しました。そして参院選で外国人排他主義を掲げた参政党が大勝したことを念頭に、「日本市場の持続的な開放がもたらされる可能性は低い」と予想しました。
他のメディアでは通信社記事の転載が多くなっていますが、読者コメントが多く寄せられています。
オンラインメディアwatson.ch外部リンクドイツ語版には、スイスの主要政党・急進民主党(FDP/PLR)と国民党(SVP/UDC)が「トランプ氏の脅迫に屈している」として、「トランプ氏が相当な額を搾り取ることができるのはスイスからだけだ」と悲観的な声が寄せられました。(出典:SRF外部リンク、フィナンツ・ウント・ヴィアトシャフト外部リンク/ドイツ語)
参政党・神谷氏の成功 スイスメディアの分析
参院選後、スイスメディアでは参政党の躍進にますます注目が集まっています。NZZは2本の解説記事が。中国担当のカトリン・ビュッヘンバッハー記者は、「日本版ドナルド・トランプ」と題する記事で、神谷氏の経歴や人柄に注目しました。参政党はまだ小政党であり、極右ポピュリスト(大衆迎合主義者)や「騙されやすい国粋主義者」と批判される一方、「神谷氏の政治的才覚は過小評価されやすい」と強調。伝統的な有権者ではなく、「自身の築いたメディア帝国を通じてネット上の若者にアピールしている」。70年近く日本を支配してきた自民党にうんざりした有権者の間で支持されている、と分析しています。
神谷氏の掲げる減税や地域産業の強化、移民制限はトランプ氏の「MAGA(米国を再び偉大に)」に似ているとしながら、「神谷氏はトランプ氏のようなスローガン主義者ではない」とも。神谷氏はソフトで思慮深く、笑顔も見せるが、「密室では荒々しく、権威主義的に党を率いているらしい」として、同氏の元秘書が2023年に自殺したことなども紹介しました。
また「神谷氏が有権者に支持されているのは、移民受け入れに対する厳しい姿勢だけではない」。両親から引き継いだスーパー経営に失敗したことや、中学教師から政治家への転身直後は自民党から出馬できなかったことに触れました。「神谷氏のような人物の台頭は、多くの日本人が無力感を感じ、変化を望み、政府を信頼しなくなっていることを示している」
NZZの特派員責任者マルコ・カウフマン記者が執筆したコラムは、参政党の勝利は「日本にとって有益な衝撃だ」と論じています。参政党に対抗した自民党が、外国人政策を司る司令塔組織の設置という「無力なジェスチャー」しか提示できなかったことや、インフレや裏金問題にも有効な手立てを打てなかったこともあり、「腐敗した政治システムに変化を求める気持ち」が参政党対象につながった、と分析しています。
その気持ちは「正当なことであり、ヒステリーを起こす理由にはならない」として、参政党の勝利を過大評価する必要はないとカウフマン氏は指摘します。ただ「伝統的な政党は、今後有権者の関心にもっと強く対応することを迫られている」とくぎを刺し、対応を誤れば参政党など他の小政党が成長し続けると警鐘を鳴らしています。
ドイツ語圏の複数の地域紙には、南ドイツ新聞で活躍するトーマス・ハーン記者の分析が掲載されました。ハーン氏は、参政党が大勝した原因は「日本が外国人嫌いであふれているからではない。日本が外国人だらけだからでもない」と断言。「自民党の保守的な教育政策により、方向性を失っているからだ」と指摘しました。
ハーン氏は、日本の学校では議論や個人の責任といった文化はほとんど教えられず、調和や勤勉、無私、従属といった価値観ばかりが重視されると指摘。また「日本の政治は長い間、世襲議員やキャリア官僚が一般有権者や企業を相手にする、とっつきにくいビジネスだった」。インフレや気候変動で経済が迷走するなかで、「多くの国民は不満を抱いているが、民主的な議論を知らない」。そのために大衆迎合主義や排他主義に走る人々が出ていると分析しています。
フランス語圏のスイス公共放送(RTS)では、フリージャーナリストの西村カリン氏が参政党を支持するアキコさんに話を聞き、支持層の姿を描きました。アキコさんのような「本来あまり政治に関心がないが、SNSを通じて意見を形成する日本人」が参政党支持者の典型で、参政党もこうした人々をターゲットに動画を拡散していると伝えています。SNS戦略のほかにも「創設者である神谷宗幣氏のカリスマ性にも助けられている」とも指摘しました。
(出典:NZZ外部リンク、NZZ外部リンク、TagesAnzeiger/ドイツ語、RTS外部リンク/フランス語)
「安っぽい誉め言葉」の裏にある外国人差別
「日本人ほど丁寧に外国人差別する人はいない」――NZZ日曜版に掲載された記事では、日本在住歴もあるフリージャーナリストのフェリックス・リル氏が自身や周りの外国人の体験から、参政党大勝の裏にある日本人の排他的な側面を探りました。
リル氏は2012年に初めて日本に住んだころから、日本人から「お箸の使い方がうまい」「日本語が上手ですね」といった「安っぽい誉め言葉」を繰り返しかけられたといいます。そして「こんな簡単なことさえ褒められる私は、どれだけ馬鹿にされているのだろう?私は欧州でナイフとフォークを上手に使える日本人を褒めるだろうか?」と自答します。
こうした「外国人に対する特別扱い」は、「外国から来た人々に自分の居場所を示す最も分かりやすい方法」だとリル氏は捉えます。リル氏の日本人の友人も、安っぽい賛辞の裏には「あなたはここでかなりうまくやっているが、決して溶け込めないだろう」という明確なメッセージが含まれている、と説明しました。
参院選で参政党が大勝したことで、「日本の外国人排斥の新たな側面が浮かび上がってきた」とリル氏は続けます。同党や対抗する自民党は外国人の犯罪性・不法性を声高に主張しましたが、リル氏は「外国人が目立つのは犯罪性ではなく、謙虚さを知らないために地元の人々よりも大声で話したり、地下鉄や怒鳴り合いで迷惑をかけたりするからだろう」とみています。
警察による職質や飲食店の入店拒否といった拒絶反応も茶飯事ですが、「白人である私は、肌の濃い人よりは敬意をもって扱われる傾向がある」。東南アジア人は建設業や小売業で働くことが多い一方、欧州人は高層ビルの銀行で働くことが多く、「日本社会が社会的評価を仕事と強く結びつけていることにも起因しているかもしれない」と指摘しました。鎖国時代に欧州から植民地支配のコンセプトを学び、開国後に東・東南アジアを支配したという歴史にも触れました。(出典:NZZ外部リンク/ドイツ語)
【スイスで報道されたその他のトピック】
スミスキー、スイスでも大人気外部リンク(7/22)
日本人登山客、ツェルマットで遺体発見外部リンク(7/22)
石破首相の退陣報道 自身は否定(7/23)
日・EU、経済協力を強化外部リンク(7/23)
日本政府、ポール・ワトソン氏の国際手配解除に抗議外部リンク(7/23)
日本の関税合意、EUの手本になる?外部リンク(7/25)
首都圏のCPI、3%下回る外部リンク(7/25)
【ショート動画】クマに扮して退治訓練外部リンク(7/26)
話題になったスイスのニュース
23日配信した「原発回帰に傾くスイス 意識されざるリスクとは」は、関西電力が福井県美浜町で新原発を建設する方針を正式発表した直後とあって、日本人読者にも多く読まれました。脱原発を決めたはずのスイスも、気候変動やエネルギー危機を背景に原発回帰に傾いています。しかし米国やフランス、英国の科学者は、原発推進論ではリスクが正しく理解されていないと警告。ウラン採掘が労働者に与える健康被害や、温暖化自体が原発の安全性を危うくしている点が見逃されていると指摘しています。

おすすめの記事
原発回帰に傾くスイス 意識されざるリスクとは
週刊「スイスで報じられた日本のニュース」に関する簡単なアンケートにご協力をお願いします。
いただいたご意見はコンテンツの改善に活用します。所要時間は5分未満です。すべて匿名で回答いただけます。
次回の「スイスで報じられた日本のニュース」は8月4日(月)に掲載予定です。
ニュースレターの登録はこちらから(無料)
校閲:大野瑠衣子

JTI基準に準拠


















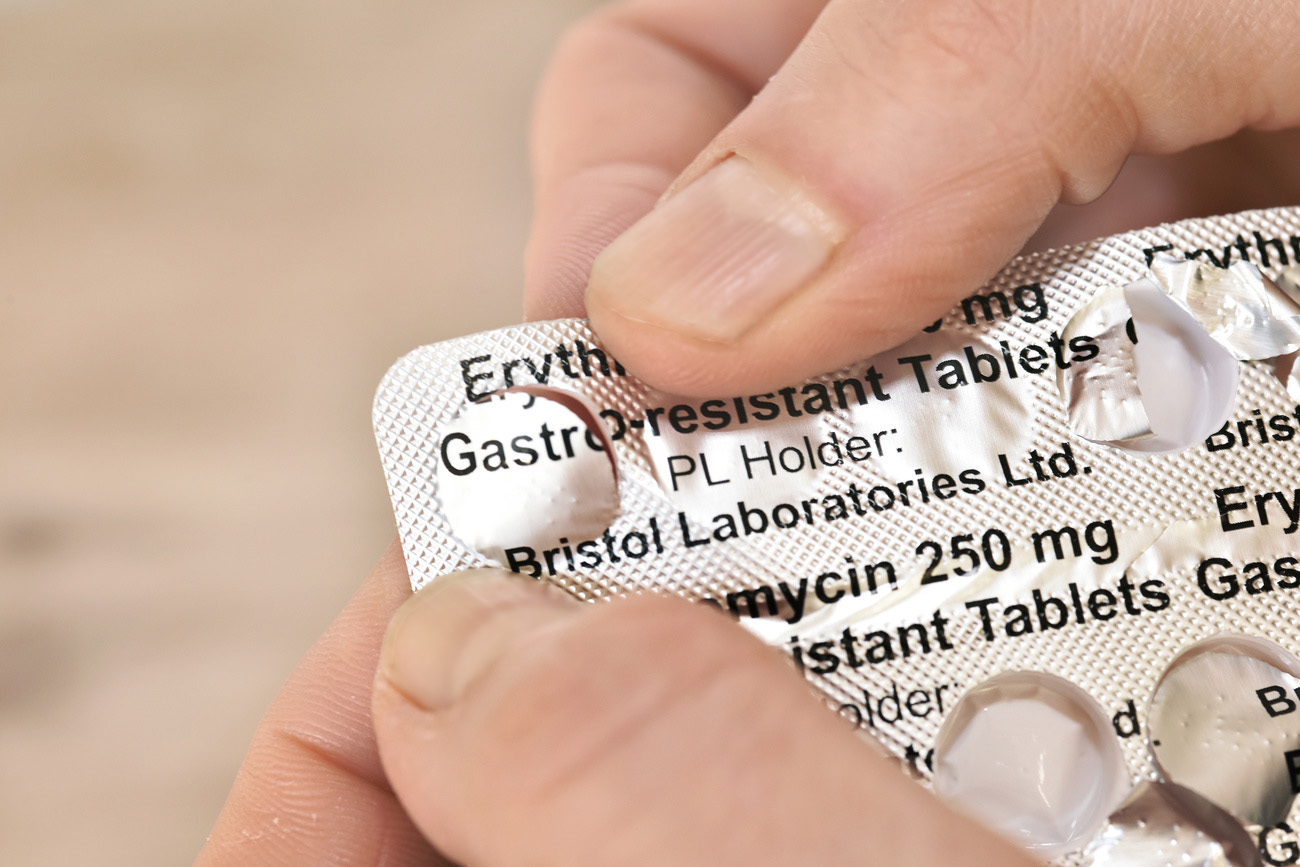

















swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。