
早期フランス語教育に終止符?スイスは分裂の危機にあるのか

スイス最大のドイツ語圏であるチューリヒ州の議会が、小学校のフランス語授業を廃止する動議を可決した。これは多言語国家・スイスの結束が弱まってきた兆候なのか?

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
「スイス人が仲良くやっていけるのは、お互いを理解していないからだ」ジャン・パスカル・ドゥラムラーズ(1983年~1998年連邦閣僚)
スイス最大のドイツ語圏、チューリヒ州の議会は9月1日、フランス語教育の開始を現行の小学校5年生から中学1年生以降に遅らせることを求める動議外部リンクを可決した。州政府は4月、動議に反対する声明を発表していた。チューリヒ州議会の決定は、これまで確立されてきたスイスの「あるべき姿」に揺さぶりをかける出来事だった。
スイスの公用語はドイツ語(全人口の62.1%)、フランス語(22.8%)、イタリア語(8%)、ロマンシュ語(0.5%)の4つ。そしてこれらの言語には、それぞれ特有の文化やメンタリティが不随する。
こうした多様性に富んだ国を1つにまとめるには強い意志が必要だ。スイス人が自国を好んで「意志の国家」と呼ぶ所以だろう。このためスイスでは第二公用語教育が重視され、ドイツ語圏であればフランス語、フランス語圏であればドイツ語というふうに、通常は小学校3年生で「第二公用語」、小学校5年生で3つ目の外国語の授業(ドイツ語圏では通常英語)が始まる。ドイツ語圏では小学校でのフランス語教育を「早期フランス語教育(Frühfranzösisch)」と呼ぶ。
一方、チューリヒ州は2005年以降、小学校3年生から英語、5年生からフランス語を学ぶカリキュラムに変更した。
州が管轄するスイスの学校教育
ドイツ語・フランス語圏が共存するスイス南部ヴァリス(ヴァレー)州のクリストフ・ダルベレー教育局長(中央党、Die Mitte/Le Centre)は、「これは私たちの基盤を揺るがすものだ」とドイツ語圏スイス公共放送(SRF)に語る。「国の結束が危ぶまれる。共通の言語が話せない状態で、どうやって共に生きろと言うのか」
同氏は州教育委員会代表者会議(EDK/CDIP)の議長も務める。スイス全州の教育局長で構成される、スイスの教育制度を監督する強力な組織だ。
スイスでは各州が学校教育を管轄する。スイスの州は全部で26州あり、各州が独自に優先事項を決定できる。しかし2006年の連邦憲法改正で、初等教育は国の管理、監督下に置かれること、また州間の調和が取れない場合は必要な規定を設ける権限が連邦に与えられた。
連邦憲法では基礎教育を州間で統一化するよう定める。そのため各州はEDK主導のもと、スイスの教育政策がより安定し、透明で理解しやすくなるよう努める。
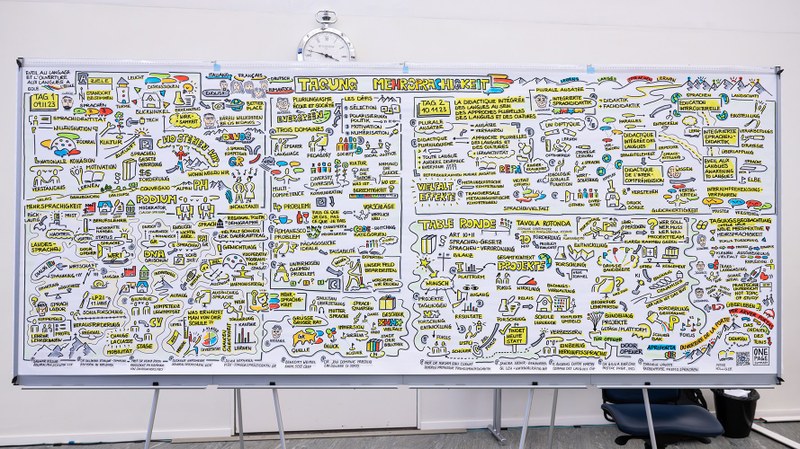
なぜチューリヒの決定が物議を醸すのか
早期フランス語教育は「ハルモス協定」外部リンクの一環で実施されている。ハルモス協定は義務教育の調和に関する州間協定で、共通の教育基準を作成するためにEDKが策定した。EDKが推進する言語戦略外部リンクにも明記されている。それによると小学校では外国語を2つ習得し、1つ目は3年生から、2つ目は5年生から授業がスタートする。
チューリヒ州で早期フランス語教育が廃止されれば、ハルモス協定から外れる。他の全ての州に影響が及ぶのは必至だ。これまで各州が地道に築き上げてきた妥協案にも大きな打撃となるだろう。
問題は、スイス最大のドイツ語圏の州が早期フランス語教育の廃止に動いたことだ。同言語圏では規模の小さいウーリ州やアッペンツェル・インナーローデン準州は、早期フランス語教育を一度も導入していない。だがこれは連邦主義のもと甘受されてきた。
だがチューリヒとなれば話は別だ。スイスでは、フランス語圏とドイツ語圏の間で見られる言語や文化の違いを「レシュティの溝」と呼ぶ。これを機に、その溝が更に深まるかもしれない。
1つにまとまろう、という意志で築き上げてきた国の基盤が、崩れ始めているのか?
連邦政府は早期フランス語教育を義務化できる?
エリザベット・ボーム・シュナイダー内務相は、まさにその点を懸念する。この動きを「不穏な兆候」とみなし、連邦憲法第70条に基づく言語法外部リンクの拡大も視野に入れる。
言語法拡大に踏み切れば、2つ目の公用語を小学校の必須科目にするよう各州に義務付ける新たな手段が生まれる。だが同時に、これは連邦政府が州の主権領域に介入することになり、連邦制に反する「原罪」にもなりかねない。
アッペンツェル・アウサーローデン準州は、チューリヒ州より一足先に早期フランス語教育を廃止した。チューリヒ州以外では、バーゼル・シュタット、バーゼル・ラント両準州、トゥールガウ州、ザンクト・ガレン州など他10州で廃止に向けた動きがある。
ドイツ語が公用語の州が相次いで早期フランス語教育を廃止する可能性があることについて、ボーム・シュナイダー内務相は6月の国民議会(下院)で「その場合は連邦政府が介入せざるを得なくなると思う」と述べた。
賛成派の見解
ヴァレリー・ピレー・カラール下院議員(社会民主党、SP/PS)は連邦政府の介入を期待する。「ドイツ語圏の州が相次いで早期フランス語教育を廃止しようとしている。これは、私たちの多様性と結束を脅かすものだ」
同氏はフリブール州(フランス語が主な公用語)出身。今年6月、政府に窮状を訴える質問状外部リンクを議会に提出した。「14年前から連邦議会に身を置くが、ここでも言語能力の低下を感じる。相手を理解できないと、妥協点を見つけるのが今以上に難しくなる」
反対派の主張
一方、バーゼル出身(ドイツ語圏)のカティア・クリスト下院議員(自由緑の党、GLP/PVL)は、国民の結束が失われるという主張は的を得ていないと反論する。教育政策が専門の同氏は、イタリア語が公用語のティチーノ州を例に挙げ「この理屈でいけば、ティチーノ州との共存関係は全く成り立たないことになる」と指摘する。
また「早期フランス語教育の反対派は、フランス語を軽んじているわけではない。むしろ強化するために試行錯誤している」と話す。重要なのは、義務教育終了時の言語習得状況が良いことだ。早く始めても、語学の上達に必ずしも繋がるわけではないことは研究外部リンクからも明らかだとした。
クリスト氏は教育上の考察と科学的な知見から、長年にわたり外部リンク早期フランス語教育に反対してきた。地元バーゼル・シュタット準州では、小学校3年生からフランス語教育が始まる。授業は「没入型学習(イマージョン)」をベースとし、この年齢の子どもの発達段階に合わせて特別に開発された教材を用いて行われる。
だが週2~3時間の授業では、このコンセプトの要件は満たせない。「(この年齢は)第一言語であるドイツ語の読み書きさえ十分に習得できていない。主要科目の算数にも悪影響が出ている」とクリスト氏は主張する。
なぜ早期フランス語教育が取り沙汰されるのか?
クリスト氏の指摘は、実は多くの人が薄々感じている。小学校が学習目標を達成できなくなってきているからだ。363の能力項目と2304の能力レベルを盛り込んだ470ページの学習カリキュラムは、詰め込みすぎだとの批判外部リンクも大きい。
それを指し示す研究結果もある。スイス全土を対象に行われた最新の調査外部リンク(2023年)では、義務教育を終えたスイス人の18%が、自身の第一言語でも最も簡単な文章を読めないとの結論が出た。また、学力の低いクラスに所属する低学年の生徒のうち、フランス語会話で基礎レベル(一番下の初歩レベル)に達しているのはわずか11%だった。
これはかなり悪い成績だ。遊び心のある言語環境でフランス語を学ぶという、多大な労力をかけて導入された没入型学習方法に対しても厳しい評価となった。
クリスト氏は「良かれと思って行われた教育改革だったが、結果的には失敗に終わった」と話す。「そもそも没入型教育と呼べる状態に至っていない。成果が出なくて当然だ」

5年生より前に外国語の学習を始めることに意味はあるのか?
ひとことに「早期フランス語教育」と言っても、スイスでは地域によってその内容が異なる。フランス語の授業が3年生から始まる州もあれば、5年生からの州もある。だが始まるタイミングが3年生か5年生かでは、教育学的観点から大きな違いがある。
スイスの3年生は通常9歳。文法構造から言語を学ぶ能力がまだ備わっていない年齢だ。そのため子どもたちは「子どもらしい」没入型、つまり言語を使う生活環境の中に入ることで言葉を学んでいく。
一方、批評家らは、スイスの小学校にはこの種の学習を実現できる枠組みが整っていないと指摘する。測定可能な学習効果を得るためには、授業の半分をその言語で行う必要があるという。
5年生からは、語彙、文法、構成的な順序など、体系的な言語学習が可能になる。
解決策は?
アールガウ州教育局長を務めるマルティナ・ビルヒャー下院議員(国民党、SVP/UDC)も、この燦々たる結果を前に「放置できるレベルではない」と日刊紙NZZに述べた。
具体的な数値で言えば、アーガウ州の生徒は義務教育終了までにフランス語の授業を585回受ける。これは生徒1人当たり15万5000フラン(約2900万円)の費用が発生することを意味する。それにもかかわらず「職業進学を前提とした中卒生徒のうち、基礎的なレベルに達しているのはわずか7%。残りの93%は、簡単なフランス語の文章さえ理解できない」と嘆く。
これに対しピレー・カラール氏は「目標を達成できていないと言うが、(早期フランス語教育を止めて)授業を減らせば、より目標に近づけるのか?」と反論する。
また反対派の矛先は、早期フランス語教育ではなく、フランス語そのものに向けられていると続ける。例えば早期英語教育は、同じようにカリキュラムへの負担が大きいにもかかわらず、それを疑問視する人はいない。「英語ばかり優先しておきながら、なぜフランス語は上達しないのかと首をかしげている」
これは、あらゆる考察に共通する重要なポイントだ。つまり「子どもにとってその言語はどんなメリットがあるか」という視点だ。フランス語圏の小学校で行われるドイツ語の授業が議論の対象とならないのは、メリットが明らかだからだ。ドイツ語はフランス語圏の子どもたちにあまり好かれていないが、スイスで最も多く話されている公用語であり、将来的には就職の幅を広げることにも繋がる。
一方、ドイツ語圏の人々にしてみれば、むしろ英語の方が実用的で、何より親しみやすい。そのため公用語のフランス語は、拡大を続ける英語に追いやられている。そしてその英語の広がりに対し、特にフランス語圏の人々は懸念を抱いている。
これに対しピレー・カラール氏は、スイスには生徒交換プログラムや語学研修など、フランス語の学習をより魅力的にする手段や機会があると話す。 他にも、オンラインディスカッションやビデオ会議、サマーキャンプなどがフランス語の促進に向けEDKで議論されている。

おすすめの記事
スイスの政治
編集:Samuel Jaberg、独語からの翻訳:シュミット一恵、校正:宇田薫

JTI基準に準拠























swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。