
ヒバクシャもジュネーブも止められない核開発競争

広島・長崎への壊滅的な原爆投下から80年、世界の核兵器関連支出は増すばかりだ。今や希少な存在になった被爆者たちは、何が危機に瀕しているかを世界に向けて訴え続けている。

おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
1945年8月6日、広島。当時7歳だった児玉美智子さんは教室の窓際の机にしがみつき、外に出るか、そのままじっと防空頭巾に隠れるかで迷っていた。その時、閃光が走った。「黄色、オレンジ、銀色」。言葉では言い表せない何かだった。窓ガラスは割れた。児玉さんは机の下に潜り込み、意識を失った。
児玉さんの学校は爆心地からわずか4㎞ほど、自宅はさらに近かった。父親が彼女を背負って炎上する街を通り抜けると、焼け焦げた遺体が次々と現れた。
「あの光景は今でも私の記憶に焼き付いています」。児玉さんはスイスインフォの動画インタビューで語った。「人々が私たちの足をつかんで、『助けてください。水をください』と訴えてきました」
特に衝撃的だったのは、おそらく家族とはぐれた同い年くらいの少女が駆け寄ってきたことだ。顔と体の半分が焼け焦げ、通り過ぎる人たちに、どうすることもできない目で訴えかけていた。児玉さんが振り向くと「彼女はすでに地面に倒れていました。亡くなったのだと思います」。
80年経った今、児玉さんの証言は、たった1つの核兵器がもたらした壊滅的な被害を予見させるものだ。史上初めて戦争に使用された原子爆弾は、広島の約10㎞²を破壊し、推定13万5000人の命を奪った。児玉さんの経験談は、新たな核軍備競争に突入する分裂した世界への警告でもある。専門家は、この競争が世界に破滅をもたらしかねないと警告する。
おすすめの記事
80年間消えない地獄 「核なき世界」訴える広島の被爆者

ジュネーブでの軍縮交渉の停滞から軍事予算の急増に至るまで、もはや核兵器廃絶ではなく再軍備へと向かう流れが生まれている。過去5年間で世界の核兵器関連支出は急増しており、1945年以降、世界は多くの人が認識している以上に核戦争の危機に瀕してきた。
「核兵器が使用されるリスクは今、かつてないほど高まっています」。ジュネーブを拠点とする組織核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)のメリッサ・パーク事務局長はこう語る。ICANは核兵器を包括的に禁止する初の国際協定、核兵器禁止条約(TPNW)の推進に貢献し、2017年にノーベル平和賞を受賞した。
パーク氏の懸念は広く共有されている。原子科学者会報は1月、終末時計の針を1秒進め、午前0時まであと89秒とした。危険な技術が世界にとって存亡の危機となるという、これまでで最も厳しい警告だった。ロシアのウクライナ戦争が誤算や事故によって核戦争に発展する恐れへの懸念を反映している。
その後、5月には核保有国インドとパキスタンの間で緊張が高まり、6月には核保有国イスラエルと米国が核開発を進めるイランを攻撃した。イランは核兵器ではなくエネルギー供給など平和目的の開発だと主張している。
仏国際関係研究所(IFRI)の抑止力・拡散プログラム責任者、エロイーズ・ファイエ氏は「国家統治と威圧の手段としての核兵器の復活と、国際秩序、特に核兵器をめぐる規範や規制の世界的な崩壊」を懸念する。こうした状況は、コミュニケーションの誤りや壊滅的な過ちのリスクを高めるとみる。
新たな軍拡競争
近年、核兵器への支出は急増している。2019年以降、核兵器保有国9カ国(米国、ロシア、中国、フランス、英国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮)はすべて、年間投資額を増やした。米国がトップで、ロシアと中国が僅差で追随する。
米国防総省によると、中国は2000年代初頭の約200発から昨年の時点で推定600発まで核弾頭保有数を大幅に増やした。30年までに1000発以上に増加すると予測されるが、それでも米国とロシアの備蓄量の1割程度に過ぎない。
中国政府は、公式には「核兵器の先制不使用」政策を掲げ、先に攻撃されない限り核兵器を使用しないと誓っている。だが西側諸国の一部アナリストは、大規模な紛争が発生した場合にこの姿勢がどの程度堅固に維持されるのか疑問視する。
IFRIのファイエ氏は、「既存の核保有国による核兵器への関心の高まりは、核兵器を保有していない国々に新たな発想を与えています」と話す。核兵器に対してより好意的な姿勢を強めている国々として、韓国、日本、ウクライナ、トルコ、サウジアラビアを挙げ、「これらの国々は核兵器を国家運営の有用な手段とみなしているのです」と説明した。
核兵器の近代化は新たな危険をもたらす。多くの核保有国は極超音速ミサイルやAIを活用した照準システムを開発している。パーク氏は特に、核指揮統制システムへのAIの浸透と、近代化によってこれらのシステムがサイバー攻撃に対してさらに脆弱になることを懸念する。
今日の核弾頭は小型化されているものの、米国が広島と長崎に投下した核弾頭に比べると飛躍的に強力だ。米国が1954年に実験した水爆「ブラボー」の威力はTNT換算で15メガトンと、広島原爆(15キロトン)の1000倍だった。当時の破壊力に今日の1万2000個の核弾頭を掛け合わせると、その潜在的な壊滅状態が想像できる。児玉さんは「1万2000個の核弾頭があれば、地球は2倍以上破壊される可能性があります」と話す。

危機に瀕する条約、後退する規範
ヒロシマ以来苦労して築き上げられた核抑制の構造は、揺らぎつつある。
1960年代にジュネーブで交渉された核兵器不拡散条約(NPT)は、信頼性の危機に直面している。2022年に開催された前回の再検討会議は合意に至らず決裂し、2026年に予定されている次回会議の見通しも暗い。
ニューヨークで5年ごとに開催される再検討会議は、核不拡散、軍縮、原子力の平和利用という条約の3つの柱の進捗状況を評価し、署名国間の約束を強化することを目的としている。
ICANのパーク氏は「軍備管理協定はほぼ完全に崩壊し、新たな核軍拡競争が始まっています」と話す。「非常に深刻な事態です。今こそ、世界の指導者たちが互いに話し合い、不信感を薄め、久しぶりに真剣に軍縮について議論すべき時です」
ジュネーブは今年、広島・長崎原爆投下80年を記念する複数のイベントを開催している。スイスの中立性に関する評判と、国連軍縮研究所など主要な国連機関のホスト都市としての立場を考えると、核問題に対処しようとする国々にとって自然な選択であった。
1986年にウクライナのチェルノブイリ原子力発電所で発生した原子力事故は、スイスで強力な反核運動を引き起こし、世論と長期的なエネルギー政策に大きな影響を与えた。事故後、ジュネーブは原子力安全と災害対応に関する国際調整の拠点となった。
ジュネーブは核外交において象徴的な中心的な役割を担い、水面下での交渉の信頼できる場として機能する。その重要な例の一つが、2015年のイラン核合意(包括的共同行動計画=JCPOA)だ。イランに対し、国際制裁の解除と引き換えに核開発計画を大幅に縮小することを義務付けた。
ロシアは年3回の会合を開く国連軍縮会議の開催地でもある。だが過去数十年、新たな条約を締結していない。直近の主要な条約である包括的核実験禁止条約は1996年に署名されたが、必要な批准国を得られず発効せずにいる。米国、中国、インドなどの主要国は条約を批准しておらず、ロシアは2023年に正式に批准を失効させた。
2021年に発効した核兵器禁止条約(TPNW)は、すべての核保有国によって無視され続けている。中立国スイスでさえ、人道的要請にもかかわらず、署名を見送っている。スイス連邦議会は24年3月に発表した最新の評価において、スイスの核抑制へのコミットメントは、すべての核保有国を含む既存のNPTを通じて追求するのが最善であると再確認した。
紛争地域が高める核リスク
世界は、1962年のキューバ危機からレーダーの誤報に至るまで、多くの人が認識している以上に何度も核大惨事の瀬戸際に立たされてきた。パーク氏は、世界は「全くの幸運」のおかげで生き延びてきたと述べる。ガレス・エバンス元国際核不拡散・軍縮委員会(ICNNC)共同議長や国連アントニオ・グテーレス事務総長らも同じ意見だ。
最も危機的状況に陥ったのは、冷戦時代に膨大な核兵器を蓄積した米国と旧ソ連の関係だ。両国はそれぞれ数万発の核弾頭を保有していた。現在も米国とロシアはそれぞれ5000発以上を保有し、世界全体の核兵器の約9割を占める。
今日の最も不安定な地政学的紛争には、核兵器保有国、あるいは核兵器の取得に迫られている国が関与する。
パーク氏は「現在、核兵器保有国を巻き込んだ大規模な紛争、核の脅威、そして非常に高位の政治指導者たちによる核に関する発言の増加といった問題が起こっています」と指摘する。「核兵器は、それを保有する国々によって、核による威圧、つまり核による威圧のために利用され、責任を負わないという姿勢を示すような行動をとっている」
同士は、米国とイスラエルによる最近のイランへの攻撃は、世界の核政策の二重基準を浮き彫りにしたと指摘する。それでもTPNWへの支持が高まりつつあることに、希望を見出す。TPNWは国連で過半数の支持に近づいており、すでに100カ国近くが署名または批准した。キルギスなどさらに多くの国が今年中に批准すると予想されている。
無視される過去の教訓
児玉さんら被爆者にとって、核の脅威は痛ましいほど現実であり、あまりにも身近な存在だ。児玉さんは心に深く刻まれた過去の記憶を背負い、その使命感と、世界が広島の惨禍を忘れつつあることへの懸念から、声を上げ続ける。
その懸念は理解できる。2018年、児玉氏は核保有国5カ国の外交官と会談し、NPTに基づく軍縮義務の履行を強く求めた。だがウクライナ紛争が続く中、2024年にジュネーブに戻った際、これらの国の代表は面会に応じず、会えたのは非核保有国の代表のみだった。
ウクライナからの映像、特に紛争で命を落とした子どもたちが遺体袋に入れられる様子は、児玉さんにとって特に辛いものだった。「当時、広島にはビニール袋さえありませんでした。手足がなく、男女の区別もつかない焼死体が荷車に積み込まれ、ゴミのように扱われました。彼らには人間としての尊厳など全く残っていませんでした」
児玉さんは、日本の現状にも失望している。核攻撃を受けた唯一の国であるにもかかわらず、日本はTPNWに署名していない。同条約が発効した2021年に、原爆投下当時5歳だった児玉さんの弟は放射線被曝に起因する複数のがんを併発し亡くなった。
「私たちヒバクシャはまだ生きています」と児玉さんは語気を強める。「私たちは怒っています。核兵器のない世界を願っています」
おすすめの記事
追加取材:上原亜紀子、編集:Nerys Avery/vm 、英語からのGoogle翻訳:ムートゥ朋子

おすすめの記事
【友だち募集中】スイスインフォ日本語版 LINE公式アカウント
外部リンク
JTI基準に準拠


















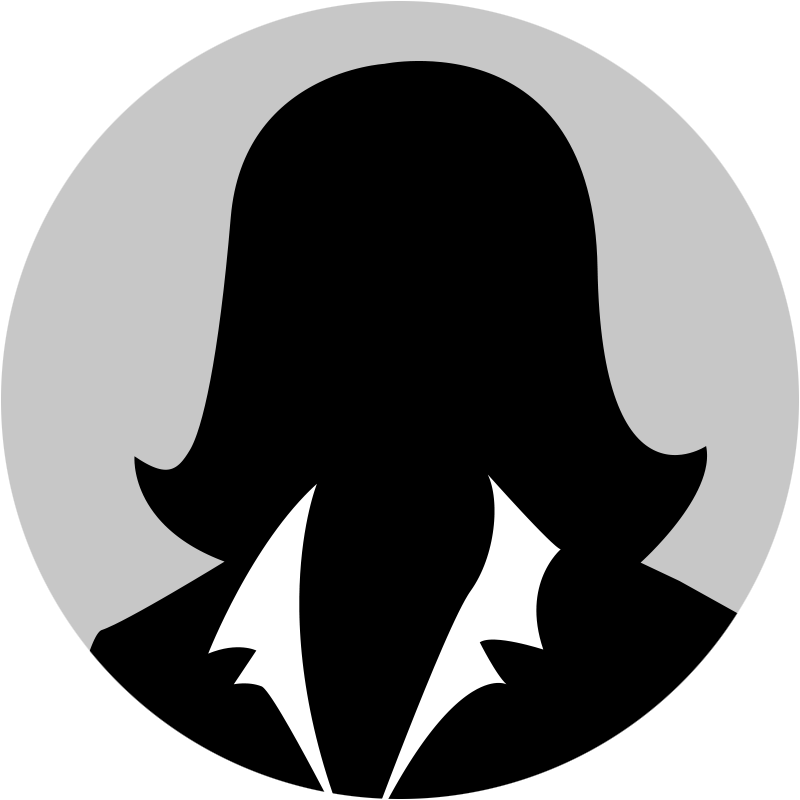
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。