
スイスの気候学者、政府の対策に厳しい評価 国内で最大4.5度上昇を予想
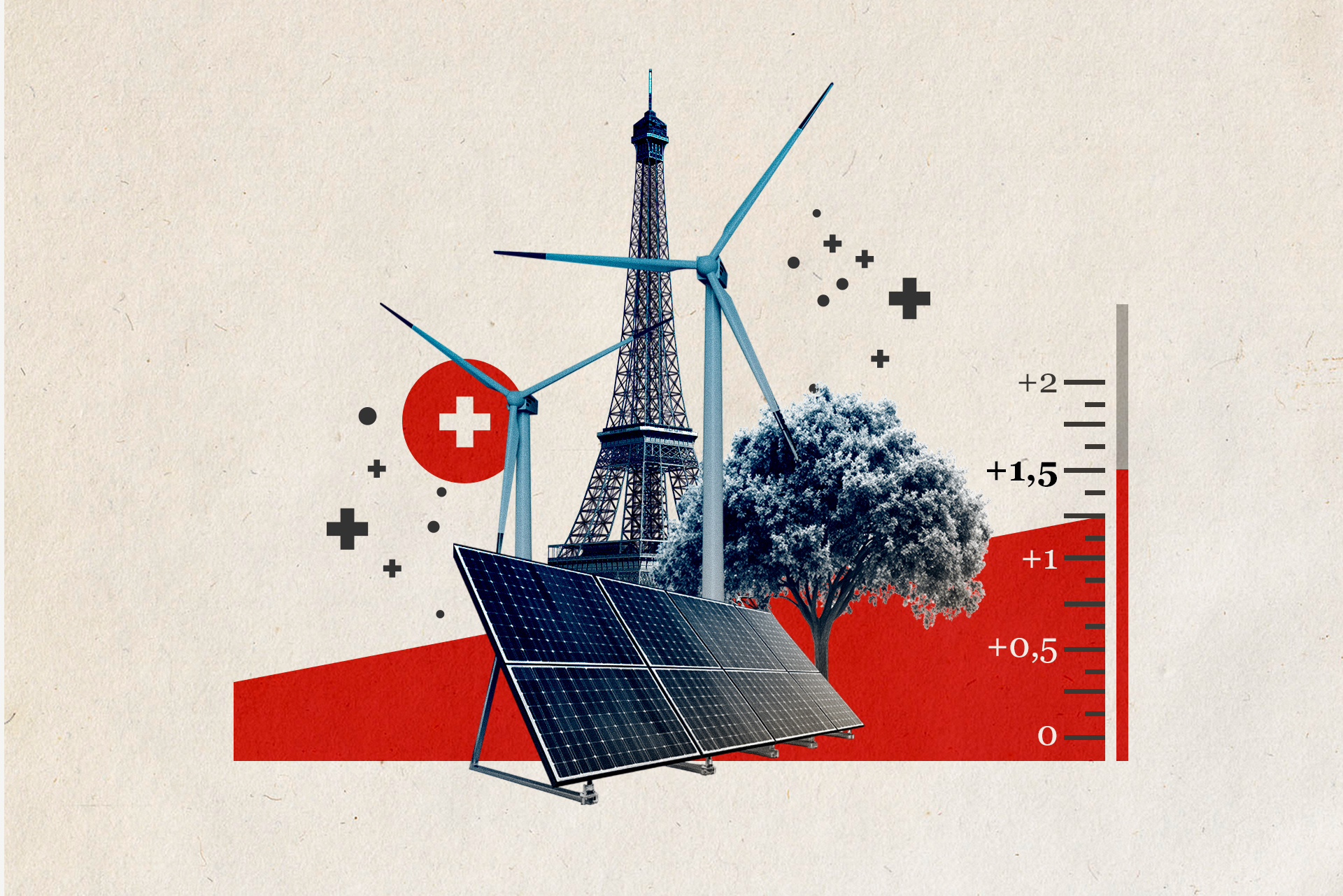
2015年にパリ協定が採択されてから10年。スイスの気候科学者を対象としたアンケート調査では、世界が気温上昇を1.5度以下に抑えることはもはや期待できないとの意見が大勢を占めた。2100年までの気温上昇幅としては、2.5度を予想する人が最多だった。
気候研究と気候の現状に関するスイスインフォの調査に参加したのは、スイス国内の80人を超える研究者。地球の気温上昇を産業革命以前と比べて1.5度に抑えるというパリ協定が理想とする目標について、回答者のほぼ全員(95%)が達成は現実的ではないと考えている。
連載記事「パリ協定の10年」では、スイスをはじめとする各国の温室効果ガス排出量、再生可能エネルギーの導入状況、気候変動政策、気候研究の動向について紹介する。
国連のアントニオ・グテーレス事務総長も今月22日、「1.5度を超えることは避けられない。今後数年間で規模や期間の差はあれ、1.5度を上回る期間が訪れるということだ」との見解を示している。
スイス研究者たちの見通しでは、地球の気温は今世紀末までにおよそ2.5度上昇する。連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)で森林生態学を教えるハラルド・ブグマン正教授は、これが「現実的」な数字だと見ている。
そのうえで同氏は、次のように述べる。「世界の気温はすでに1.5度を超えて上昇しており、現在の地政学的状況を考慮すると、過去に設定された目標が今後も追求される望みはほとんどない。たとえ気候緩和の取り組みがグローバル規模で再び活性化することがあったとしても、これは深刻な遅れにつながる」
研究者たちの懐疑的な見解の背景には、地球上の気温が記録的な上昇を続けている現状がある。世界気象機関(WMO)によると、2024年は、世界の平均気温が産業革命前比で1.55度上昇し、目標値である1.5度を初めて超えた年となった。
もし2.5度の気温上昇という予測が現実のものとなれば、スイスにとって、さらに悪い事態が訪れることになる。地理的に気温が上昇しやすいスイスは世界平均の2倍の速さで温暖化が進行しており、これはすなわち、スイス国内で今世紀末までに4~4.5度の気温上昇が起こり得ることを意味する。
☟スイスで気温上昇が進みやすい理由は?解説記事はこちら

おすすめの記事
スイスの気温上昇、世界の2倍で進む その理由は
このレベルの気温上昇は、「アルプスの国」スイスの姿を根本から変えてしまいかねない。スイスの氷河の90%以上が消失すると予測されており、それにより河川の流れや流量が変化し、ひいては農業、水力発電、家庭向けの夏場の水供給に深刻な影響が生じることになる。チューリヒやジュネーブといった都市部では、真夏の気温が40度やそれ以上に達する可能性があり、2022年のような熱波が毎年のように発生することも考えられる。
冬季に安定した降雪量があるのはより標高の高い地域へと後退してゆき、標高の低いエリアに位置するスキーリゾートの多くは経営が立ち行かなくなることが見こまれる。
さらに、科学者たちの圧倒的大多数が、気候危機が10年前に予想されていたよりも速いペースで進行していると考えている。調査回答者の3分の2が、地球温暖化は当時予想されていたよりも「はるかに速い」「やや速い」ペースで進んでいると答えた。「おおむね予測通り」は25%だった。
スイス市民が受ける酷暑の影響
調査結果からは、研究者たちがパリ協定の採択された10年前よりも悲観的になっていることが読み取れる。回答者の6割が、気候変動の緩和のために行動しようという政治家の意欲について、当時よりも悲観的に見ていると答えた。
さらに76%は、2050年までに気候変動がスイスの生活環境に「大きな」「非常に大きな」影響を与えると予測。猛暑あるいは酷暑の頻発と激化が懸念されており、特に都市部の住民や脆弱な立場にある人々に危険が及ぶと警告している。
陸域と大気の相互作用、気候モデル、土地利用と土地被覆の変化が気候に与える影響を研究するベルン大学のエドゥアール・ダヴァン教授は、「熱波がより頻繁かつ強烈になり、特に都市部の人々の健康に影響を与えるだろう」と述べた。
同氏はまた、洪水や土石流、暴風雨などの自然災害によるインフラ被害といった、気候変動がもたらすその他の重大な懸念についても指摘している。
「永久凍土の融解や集中豪雨により、アルプスでは不安定な現象(地滑り、氷河の崩壊、雪崩など)の発生が増加する可能性がある。洪水と干ばつも目に見えて悪化し、人々とインフラに被害が及ぶことになる。また、生態系が破壊されるリスク、農作物の生産性低下のリスクも高まるだろう」と、同氏は回答している。
今なお途上のスイスの気候政策
気候変動対策へのスイスの取り組みが10年前より強化されたと思うかどうかを問う質問では、楽観視も悲観視もしていないとの回答が最多を占めた(回答者の約4割)。回答者の間では、同国の取り組みが「前進した」と考える人の数が、「そうは思わない」と考える人の数をわずかに上回った。
気候変動対策に関する画期的な枠組条約であるパリ協定から10年を迎えるにあたり、スイスインフォは2025年9月、スイスで気候変動関連研究に従事する科学者を対象に、気候研究・政策・地球温暖化の現状に焦点を当てた22の質問からなるアンケート調査を送付した。
調査票を送ったのは、以下の研究機関に所属する気候科学者108人。
連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)、ヌーシャテル大学、チューリヒ大学、ベルン大学、バーゼル大学、ジュネーブ大学、フリブール大学、ローザンヌ大学、パウル・シェラー研究所(PSI)、連邦森林・雪氷・景観研究所(WSL)、連邦材料科学技術研究所(Empa)、スイス気象台(MeteoSwiss)
このうち、80人が調査に回答した。調査結果の詳細はこちら(英語)を参照。
しかし調査対象外の関係機関の間では、スイスの気候政策は全体として「不十分」だとの評価もある。主な理由は目標と実際の行動の間の隔たりだ。非営利団体から成る科学プロジェクトとして知られ、世界の気候政策を監視・追跡するクライメート・アクション・トラッカー(CAT)外部リンクは、2035年を期限とするスイスの新たな排出削減目標について失望を表明。目標達成に必要な「野心」が欠けている、さらに国内における排出量の「実質的な削減」ではなく、炭素の吸収や削減に資する活動に投資することで排出量を相殺する「オフセット」に過度に依存していると批判している。
スイスにおける気候対策強化の主な障害のひとつとして、スイスインフォの調査に回答した科学者たちは、市民による圧力の減退と他の危機への関心の高まりを挙げている。
たとえば、チューリヒ大学で国際気候政策研究グループを率いるアクセル・ミヒャエロウ教授が、これについて次のように言及している。「気候変動という長期的な課題は、喫緊の対応が必要だと思われる複合危機が起こると、必ずと言っていいほど政治的な優先順位が低下し、後まわしにされる。「フライデーズ・フォー・フューチャー」(訳注:気候変動対策を求める若者たちによる抗議活動)によってもたらされたような社会的圧力の再燃でもないかぎり、スイスの気候政策を私は悲観視している」
同氏はさらに、今日の気候政策は「アメ」にばかり焦点が当てられる傾向があると指摘。その典型例として、財政赤字にともなう支出削減圧力のなかで続けられている、持続不可能な補助金を挙げる。補助金に代わるものとして同氏は、たとえばパリ協定第6条から導き出される炭素税のような「ムチ」が必要だと考えている。
そのうえで同氏は、「温室効果ガスの削減が世界で効果的かつ確実に実施されるようにするためには、国際炭素市場が中心的な役割を担わなければならない。この分野におけるスイスのリーダーシップは拡大され、長期的により安定したものにしていく必要がある」との見解を示している。
スイスの責任
国の豊かさ、そして世界の温室効果ガス排出量に占める割合にかんがみ、スイスは気候変動対策において主導的役割を担う特別な責任があると思うかたずねたところ、大半の研究者がその主張に同意した。50人を超える回答者(ほぼ8割)が、「強く同意する」、さらに10人が「やや同意する」と回答。他方、同主張に反対する回答は、ごくわずかにとどまった。
スイスに責任があることの根拠として、多くの回答者がスイスの経済力と国際議論への影響力を挙げた。一方で、ベルン大学のロルフ・ヴァインガルトナー名誉教授(水文学)は、スイスには「気候変動や環境問題に真剣に取り組み、具体的な施策に落としこむ政治的意欲が欠如している」との評価をくだす。
アルプスの水系や気候変動が水文学に与える影響の研究を専門とする同氏は、「我々は、変化を観察し理解することには非常に長けているが、その知識を能動的な行動に変えることは非常に不得手である」と付け加えた。
「それでもなお、スイスは先駆的な役割を果たすことができると信じている」
初の国際的かつ法的拘束力を持つ気候協定であり、すべての締結国に対して温室効果ガス排出量の削減に取り組むよう求めている。パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)において、2015年12月12日に採択された。
同協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2度より十分低く保ち、1.5度に抑える努力をする」ことが目標に掲げられた。これを達成するためには、2050年までに温室効果ガス排出量ネットゼロ(気候中立)を実現する必要がある。
同協定は196カ国が署名し、スイスは2017年に協定を批准した。日本は2016年11月に批准している。
編集:Gabe Bullard/ts、英語からの翻訳:鈴木ファストアーベント理恵、校正:ムートゥ朋子

JTI基準に準拠























swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。